消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式):記事まとめ
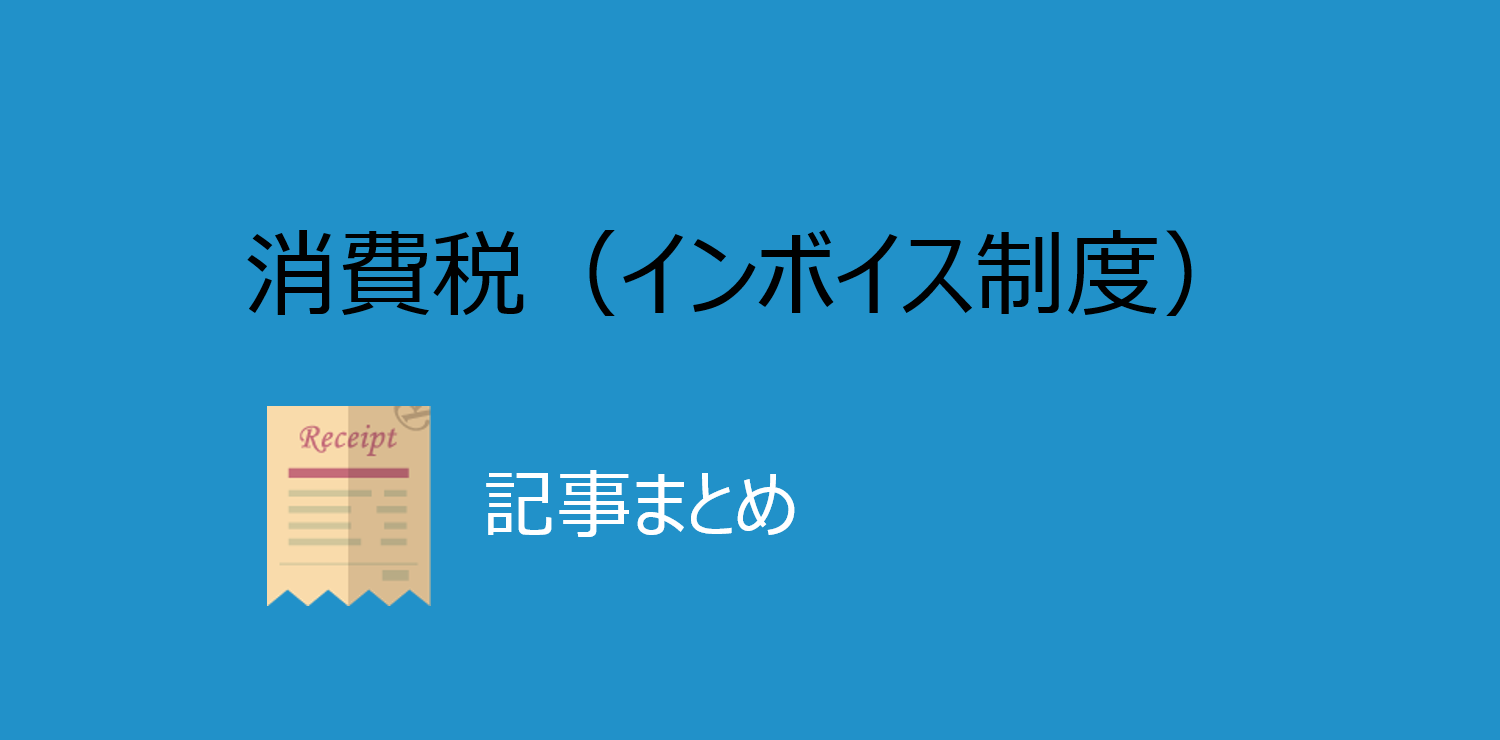
ここ最近、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)に関する記事を書いてきました。
あっという間に記事数が増えてきたので、ここまでに書いた記事をまとめます(2022年12月更新)。
Table of Contents
1.総論
まず、以下の記事で、消費税のインボイス制度に関して知っておくべき用語を5つ挙げ、制度の概要をまとめています。
その他、主に研修などで頂いたご質問にも触れています。
消費税のインボイス制度は何のための制度なのか(制度の目的)
企業(納税者)にとってのインボイス制度のメリット(消費税)
インボイス制度:購買部門で必要な対応をごく簡単に
インボイス制度:営業部門で必要な対応をごく簡単に
2.適格請求書発行事業者の登録
適格請求書発行事業者の登録については、以下の記事があります。
インボイス制度:登録番号(T+法人番号)とローマ字のTの謎
インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録手続き(令和3年10月1日から)
インボイス制度:登録日である令和5年10月1日をまたぐ請求書
インボイス制度:登録申請書の提出期限は令和5年3月31日です
インボイス制度:令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなかったら?
インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録はいつまでに行えばよいか
インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録は後からでも行えるか
インボイス制度:登録申請から登録通知までの期間
インボイス制度:適格請求書発行事業者の情報と国税庁の公表サイト
インボイス制度:適格請求書発行事業者の公表情報に変更があった場合
インボイス制度:課税期間の途中で登録した場合
インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録の取りやめと取消し
インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録をしないケース
インボイス制度:個人事業主が適格請求書発行事業者の登録をしないとどうなるか
インボイス制度:「適格請求書発行事業者ではない課税事業者」の存在
インボイス制度:新設法人の登録時期の特例
個人的に気になったのは、通達にある「ローマ字の大文字T」という表現です。ローマ字の定義を根底から覆すような斬新な表現だと思いました。
なお、おまけで以下のような記事も書きました。
インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録完了後にやるべきこと
インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録後の諸手続きと届出書
3.適格請求書などの記載事項
適格請求書や適格簡易請求書、また適格返還請求書などの記載事項については、以下の記事があります。
インボイス制度:適格請求書の記載事項+記載例をわかりやすく
インボイス制度:適格請求書は「請求書」とは限らない
インボイス制度:手書きの領収書は適格請求書に該当するか
インボイス制度:契約書はそれ自体で適格請求書に該当するか
インボイス制度:見積書は適格請求書に該当するか
インボイス制度:クレジットカード会社発行の請求明細書等は適格請求書に該当するか
インボイス制度:適格請求書上の消費税額の端数処理(切上げ・切捨て・四捨五入)
インボイス制度:適格請求書が複数書類に分かれている場合の端数処理
インボイス制度:複数契約に基づく取引をまとめた適格請求書における端数処理
インボイス制度:端数値引きがある場合の適格請求書の記載例
インボイス制度:外貨建取引における適格請求書の記載事項
インボイス制度:仕入明細書と適格請求書を1枚の書面で交付する場合
インボイス制度:適格請求書に氏名や名称に代えて屋号を記載することの可否
インボイス制度:請負工事等の値増金に係る適格請求書の交付
インボイス制度:入場券などの物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項
インボイス制度:適格簡易請求書の記載事項+記載例をわかりやすく
インボイス制度:スーパーマーケットのレシートは適格請求書に該当するか
インボイス制度:適格返還請求書の記載事項+記載例をわかりやすく
インボイス制度:適格請求書と適格返還請求書を1つにまとめる場合(前月分の値引・返品等)
インボイス制度:販売奨励金等に係る適格返還請求書の交付の必要性
以下は、おまけの記事です。
インボイス制度:登録番号を請求書に記載せずウェブサイトで記載することの可否
4.売上側(適格請求書の交付義務)
売上側(適格請求書を発行する側の立場)に関して、適格請求書の交付義務については、以下の記事にまとめています。
インボイス制度:適格請求書の交付義務と「求めに応じて」の意味合い
インボイス制度:保存すべき適格請求書等の「写し」とは
「求めに応じて」の意味合いなど、個人的に疑問に思ったことなども書いています。
5.仕入側(仕入税額控除の要件)
仕入側(適格請求書を受領する側の立場)に関して、仕入税額控除については、以下の記事にまとめています。
インボイス制度:適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
インボイス制度:3万円未満で適格請求書の保存が不要の場合
インボイス制度:3万円以上でも適格請求書の保存が不要の場合
インボイス制度:コインパーキングの利用料金に係る仕入税額控除
インボイス制度:銀行の振込手数料の取扱い(窓口・ATM・インターネット)
インボイス制度:ETC利用証明書による仕入税額控除と電子帳簿保存法対応
インボイス制度:従業員の出張旅費等に係る仕入税額控除の際の帳簿記載
インボイス制度:仕入明細書の記載事項と相手方への確認(仕入税額控除)
インボイス制度:支払通知書は適格請求書に該当するか
インボイス制度:下請業者が確認した出来高検収書による仕入税額控除
インボイス制度:水道光熱費の未払計上に係る仕入税額控除
インボイス制度:口座振替等で契約書を基礎に仕入税額控除を行う場合
インボイス制度:立替金に係る仕入税額控除には何が必要か
インボイス制度:複数社に対して交付する立替金精算書上の端数処理
インボイス制度:短期前払費用の取扱い(適格請求書の入手が遅れる場合)
インボイス制度:飲食店の領収書が適格請求書かどうかのチェック
タクシーの表示灯でインボイス交付可否がわかる近未来を思う
インボイス制度:郵便切手類による課税仕入れ(仕入税額控除)の時期
インボイス制度:物品切手等による課税仕入れ(仕入税額控除)の時期
インボイス制度:物品切手等による課税仕入れに係る支払対価の額
現行制度の「3万円未満セーフ」という取扱いからの変更点のほか、水道光熱費を未払計上する場合、契約書を基礎に口座振替等で支払いを行う場合、立替金がある場合などの仕入税額控除について書いています。
6.イレギュラー対応
以下の記事は、ちょっと目先を変えて、雑談っぽいのものです。
インボイス制度:適格請求書記載の登録番号が有効かどうかの確認
インボイス制度:適格請求書類似書類等の交付禁止及び罰則
インボイス制度:適格請求書の記載事項に誤りがあった場合の対応
インボイス制度:継続取引の場合の前月分の適格請求書の修正方法
インボイス制度:適格請求書紛失時の対応=再交付依頼
個人的に興味があったのは、適格請求書紛失時の対応です。もっとやばいことになるのかと思った。
7.税額計算
以下の記事は、雑談っぽいものから切り替わって、税額計算に関する超真面目な話です。
インボイス制度:売上&仕入税額の割戻し計算と積上げ計算
インボイス制度:仕入税額の帳簿積上げ計算の「課税仕入れの都度」とは
インボイス制度:税抜対価をベースにした仕入税額の帳簿積上げ計算
インボイス制度:外貨建取引に係る仕入税額の計算方法
インボイス制度:課税期間をまたぐ適格請求書に基づく積上げ計算
インボイス制度:仕入明細書による売上税額の積上げ計算の可否
1つ目の記事は、間違いなく、この中でいちばん退屈な記事です。
8.免税事業者(+簡易課税)
インボイス制度が「免税事業者」や「簡易課税を採用している事業者」に与える影響などは、以下の記事にまとめています。
インボイス制度:消費税の免税事業者への影響
インボイス制度:免税事業者が初年度に登録を受ける場合の経過措置
インボイス制度:個人事業者の初年度の申告対象期間
インボイス制度:免税事業者からの仕入れに係る経過措置(80%→50%)の適用要件
インボイス制度:免税事業者からの仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算
インボイス制度:基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったら?
インボイス制度:簡易課税を採用している事業者への影響
免税事業者に関するおまけの記事もあります(以下です)。
インボイス制度:免税事業者が請求書等に消費税額を記載することの可否
インボイス制度:免税事業者との取引と独占禁止法で問題となる行為
インボイス制度:免税事業者に対する値下げ交渉の可否(独占禁止法等)
インボイス制度:免税事業者に対する課税事業者への転換要請の可否
インボイス制度:免税事業者との取引停止の可否(独占禁止法)
インボイス制度:免税事業者に対して登録を取引条件とすることの可否
インボイス制度:免税事業者が登録不要のパターン4つ
インボイス制度:消滅するのは本当に免税事業者の益税か?
このおまけの記事は結構読まれているようですが、インボイス制度に関する個人的な意見は何もありませんので、念のため。
9.電子インボイス関係(適格請求書の電磁的記録による提供&保存)
以下の記事は、主に令和3年度税制改正による電子帳簿等保存法の改正の関係で書いたものです。
電子インボイス:適格請求書の電磁的記録による提供と保存(売上側)
インボイス制度:提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存形式と保存方法
電子インボイス:適格請求書の電磁的記録による保存と仕入税額控除(仕入側)
インボイス制度:請求書+EDI取引データ=適格請求書の場合
インボイス制度:支払通知書+EDI取引データ=仕入明細書の場合
10.税制改正関係
令和5年度税制改正について、いくつかピックアップして書いています(大綱レベルまでです)。
インボイス制度:3年限定で小規模事業者の納税額は売上税額の2割に?
小規模事業者の少額取引はインボイス無しで仕入税額控除可能に?
インボイス制度:売上高1,000万円&1億円以下の事業者向け経過措置の全容?
インボイス制度:課税売上高1,000万円以下の事業者の負担軽減措置(令和5年度税制改正見込み)
インボイス制度:課税売上高1億円以下の事業者の事務負担軽減措置(令和5年度税制改正見込み)
インボイス制度:1万円未満の適格返還請求書の交付義務の見直し(令和5年度税制改正見込み)
インボイス制度:1万円未満の適格返還請求書の交付義務の免除(令和5年度税制改正大綱)
インボイス制度:免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合の負担軽減措置(令和5年度税制改正大綱)
インボイス制度:売上1億円以下の事業者の事務負担軽減措置(令和5年度税制改正大綱)
インボイス制度:登録期限の実質延長で「困難な事情」の記載は不要に(令和5年度税制改正大綱)
インボイス制度:免税事業者等による登録手続きの見直し(令和5年度税制改正大綱)
11.その他諸々
以下の記事は、その他諸々、例えば、任意組合(の立替精算)や委託販売、電気通信利用役務の提供の関係について触れています。
インボイス制度:売手負担の振込手数料は値引き?立替?
インボイス制度:任意組合(JVその他の共同事業)への影響
インボイス制度:委託販売等の委託者&受託者への影響
インボイス制度:委託者&受託者における委託販売手数料部分の取扱い
インボイス制度:リバースチャージ方式(電気通信利用役務の提供)との関係
インボイス制度:登録国外事業者制度(電気通信利用役務の提供)との関係
その他、国税庁が出した手引きについても。
国税庁が適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引きを公表(2022年9月)
あと、以下のような時事ネタ(?)もちょっとだけ書きました。
インボイス制度:国税庁ウェブサイトからの公表情報ダウンロードは一時的に停止
インボイス制度:国税庁の公表サイトによる「身バレ」(本名バレ)問題
インボイス制度:国税庁ウェブサイトからの公表情報ダウンロードが再開
12.Q&Aの改訂(2022年5月追記)
2021年7月30日に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂されたので、以下の記事にまとめました。
2022年4月28日の改訂内容は、以下の記事にまとめました。
2022年11月25日の改訂内容は、以下の記事にまとめました。
13.オススメの書籍
最後に、オススメの書籍について。
制度が開始していない今、細かな論点への答えはQ&A(と税務通信さんの取材記事)がすべてだと思います。ただ、Q&Aは随時更新され、税務通信さんの取材記事もどんどん出てきます。
なので、制度の開始前に、分厚いインボイス制度の本を買うのは得策ではない気がします。
Q&Aは結構親切に書いてあり、それで足りそうにも思うのですが、唯一のネックは、全体像が見えてないと、どの部分に対応するQなのかがわかりづらいということです(たぶん構成があんまりよくない)。
このような観点から、私が個人的にオススメしているのが、熊王先生(クマオー先生)の『改訂版 Q&Aでよくわかる 消費税 インボイス対応 要点ナビ』です(紹介記事はこちら)。
安定のクオリティで、しかも、さっぱりしてて読みやすいです。
なので、これを読んだ後、Q&Aや税務通信を読むと効率的だと思います。
いったんはここまでですが、また何か思いついたときには、随時記事を追加していきます。
では、では。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
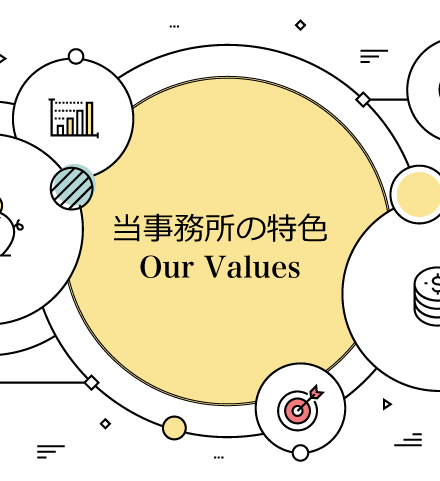
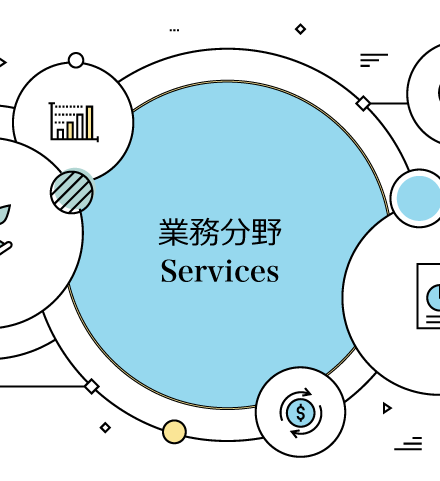
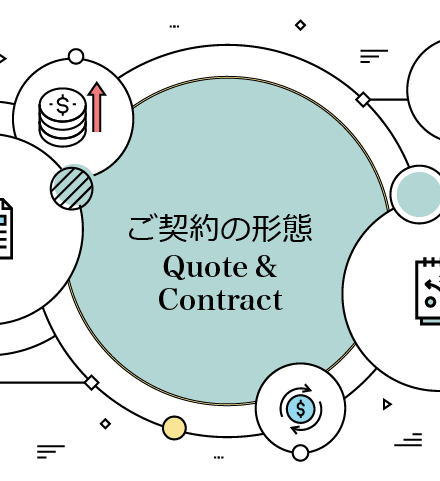
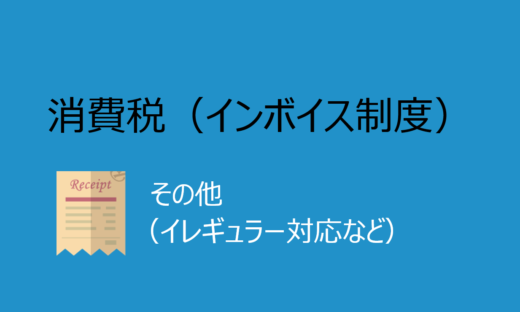
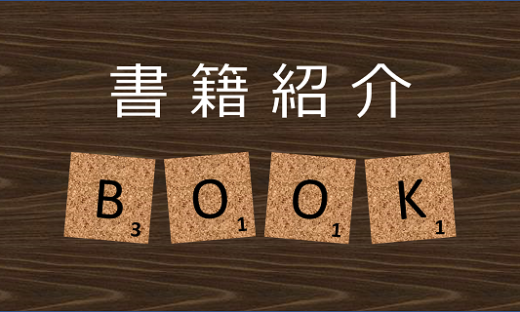
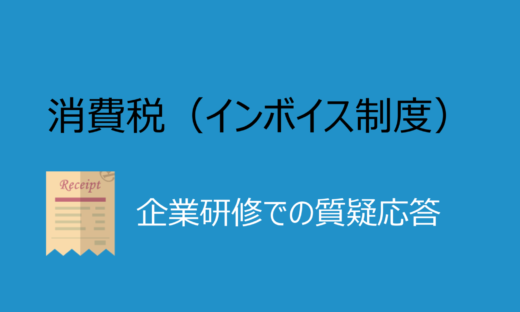
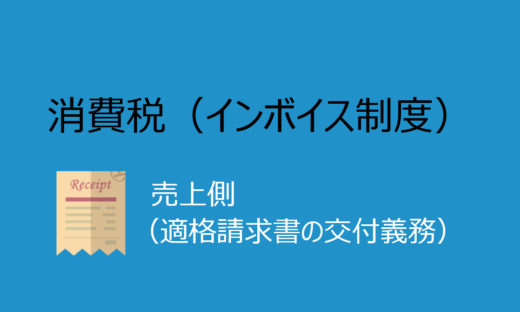
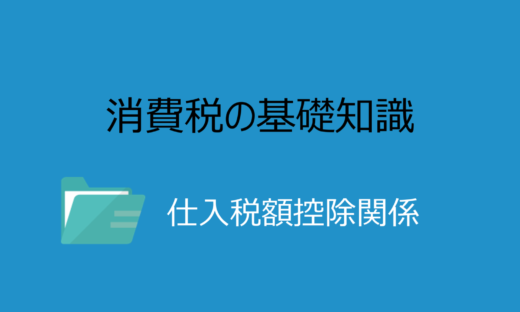
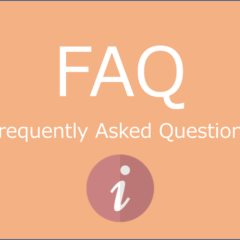


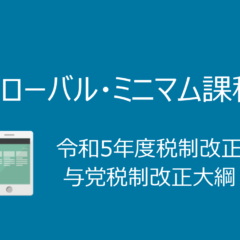
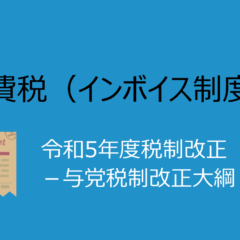
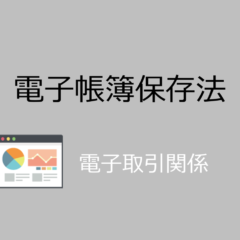
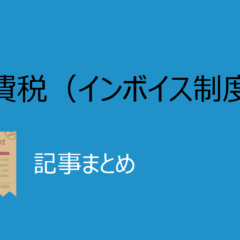

-240x240.png)
-240x240.jpg)
-240x240.png)
