インボイス制度:免税事業者からの仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算
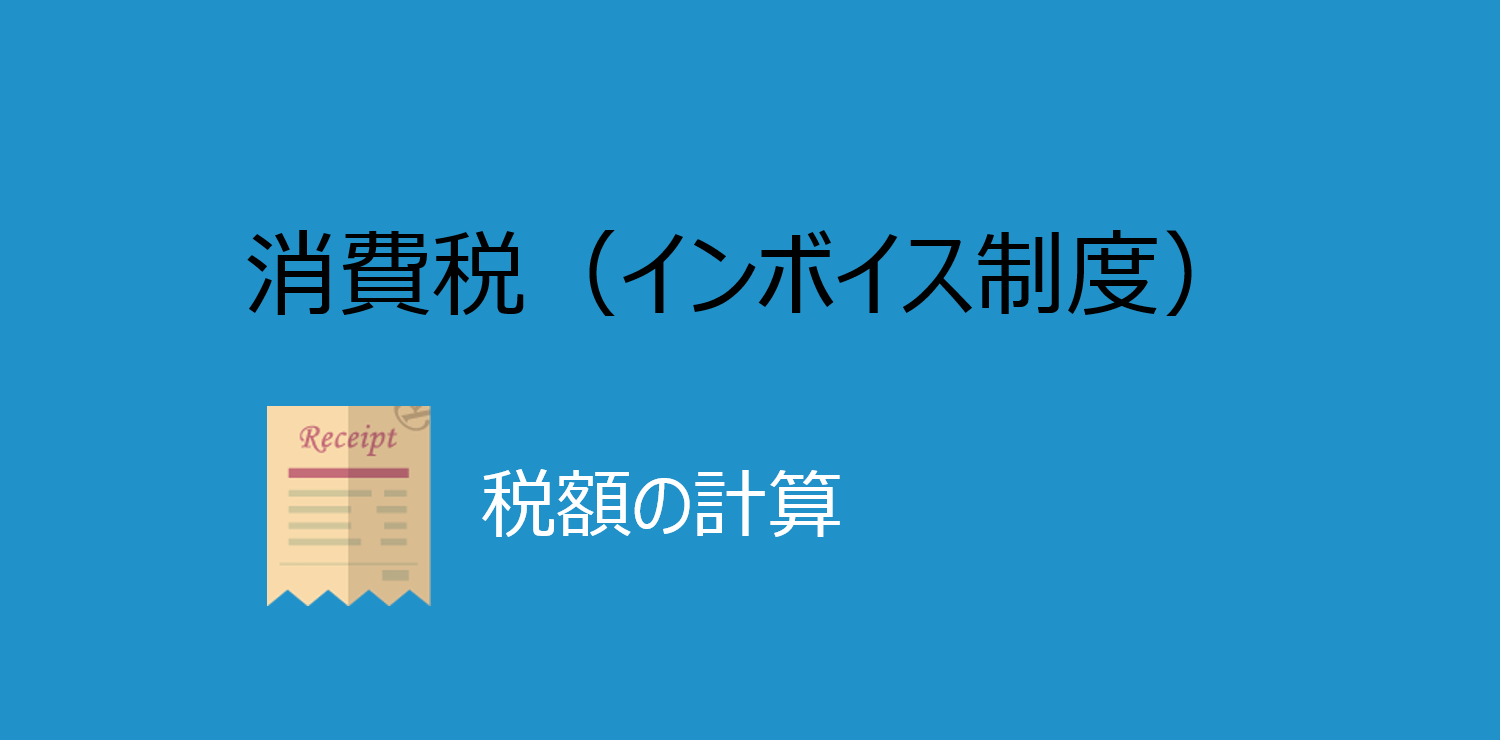
今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。
2022年4月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂され(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。
今回は、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 免税事業者からの仕入れに係る経過措置
適格請求書等保存方式の下では、免税事業者を含む適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除を行うことはできません。
しかしながら、この点については経過措置があり、適格請求書等保存方式開始後6年間は、免税事業者からの課税仕入れについても、以下のとおり、一定割合の仕入税額控除の適用を受けることができます(適用要件などはこちら)。
2. 仕入税額控除の具体的な計算方法
この経過措置を適用する場合の仕入税額控除(仕入税額とみなす金額)の具体的な計算方法については、積上げ計算と割戻し計算のどちらを適用しているかで異なります。
積上げ計算と割戻し計算の詳細については、以下の記事をご参照ください。
3. 仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合
仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合、この経過措置の適用を受ける場合においても、同様に「積上げ計算」により計算する必要があります。
具体的には、この経過措置の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に上記の割合(80%など)を乗じて算出します。
そして、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てまたは四捨五入します。
Q&Aでは、経過措置の適用を受ける課税仕入れを区分して管理し、課税期間の中途や期末において、区分した課税仕入れごとに上記の計算を行うこととしても差し支えないこととされています。
【2023年7月追記】
2023年4月のQ&A改訂により、税抜経理を採用している場合で、課税仕入れの都度、経過措置対象分(80%など)の仮払消費税額等を算出し、端数処理(切捨てまたは四捨五入)を行っていれば、その金額の合計額に100 分の78 を乗じて算出した金額(切捨て)を本経過措置の適用を受けた課税仕入れに係る消費税額としても差し支えない、という取り扱いが示されています。
4. 仕入税額について「割戻し計算」を適用している場合
仕入税額について「割戻し計算」を適用している場合、この経過措置の適用を受ける場合においても、同様に「割戻し計算」により計算する必要があります。
具体的には、課税期間中に行った経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額の合計金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を乗じて算出した金額に上記の割合(80%など)を乗じて算出します。
今日はここまでです。
では、では。
↓インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。
6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)
↓インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。
これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
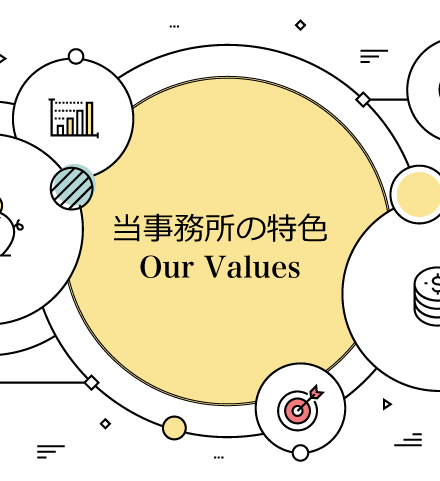
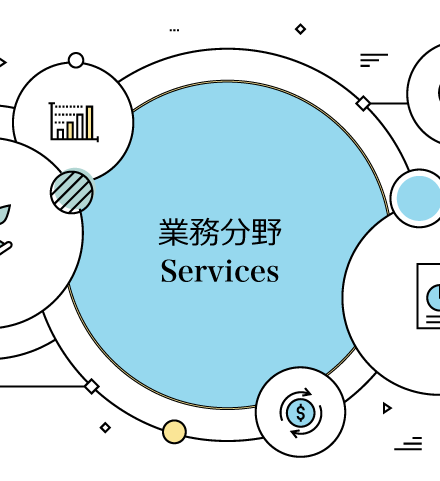
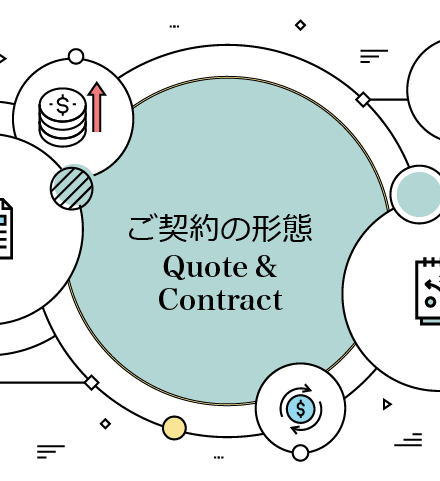
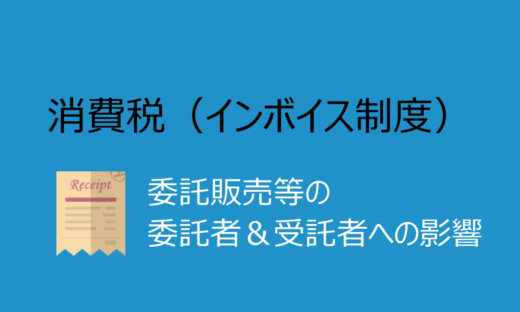
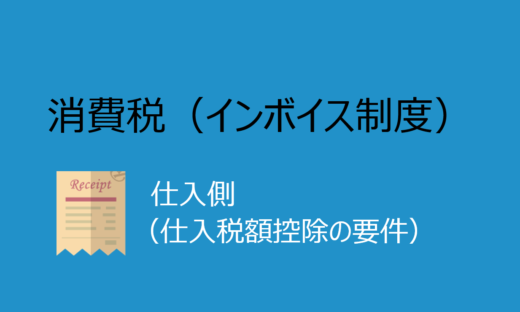
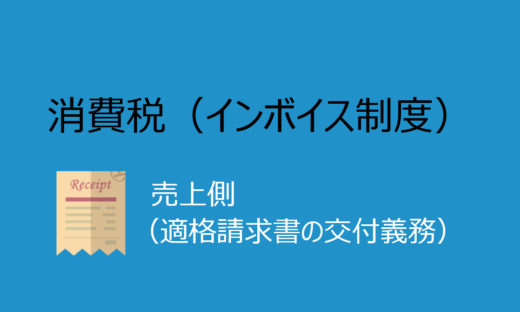
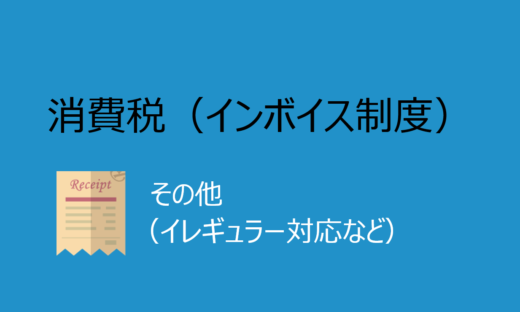
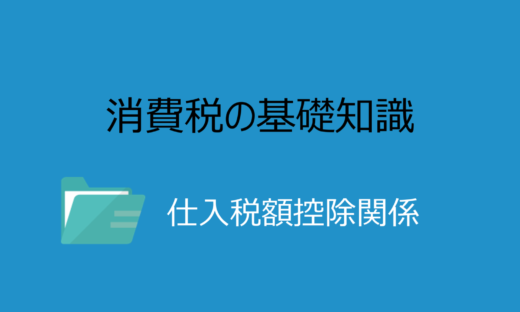
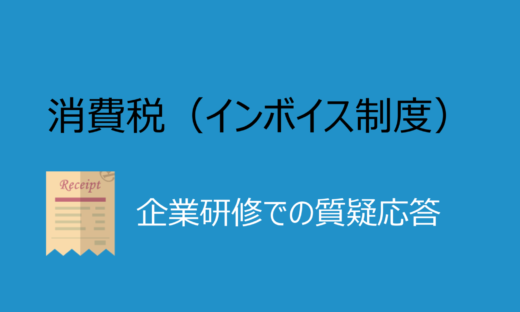


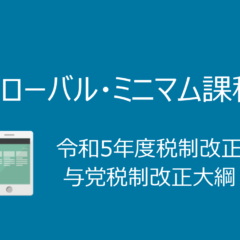
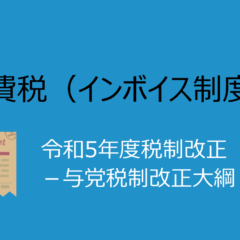
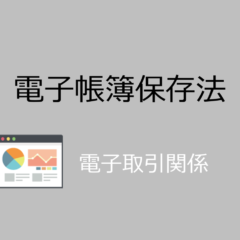
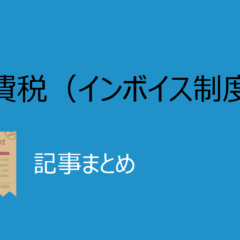

-240x240.png)
-240x240.jpg)
-240x240.png)

-240x240.png)