インボイス制度:3万円未満で適格請求書の保存が不要の場合
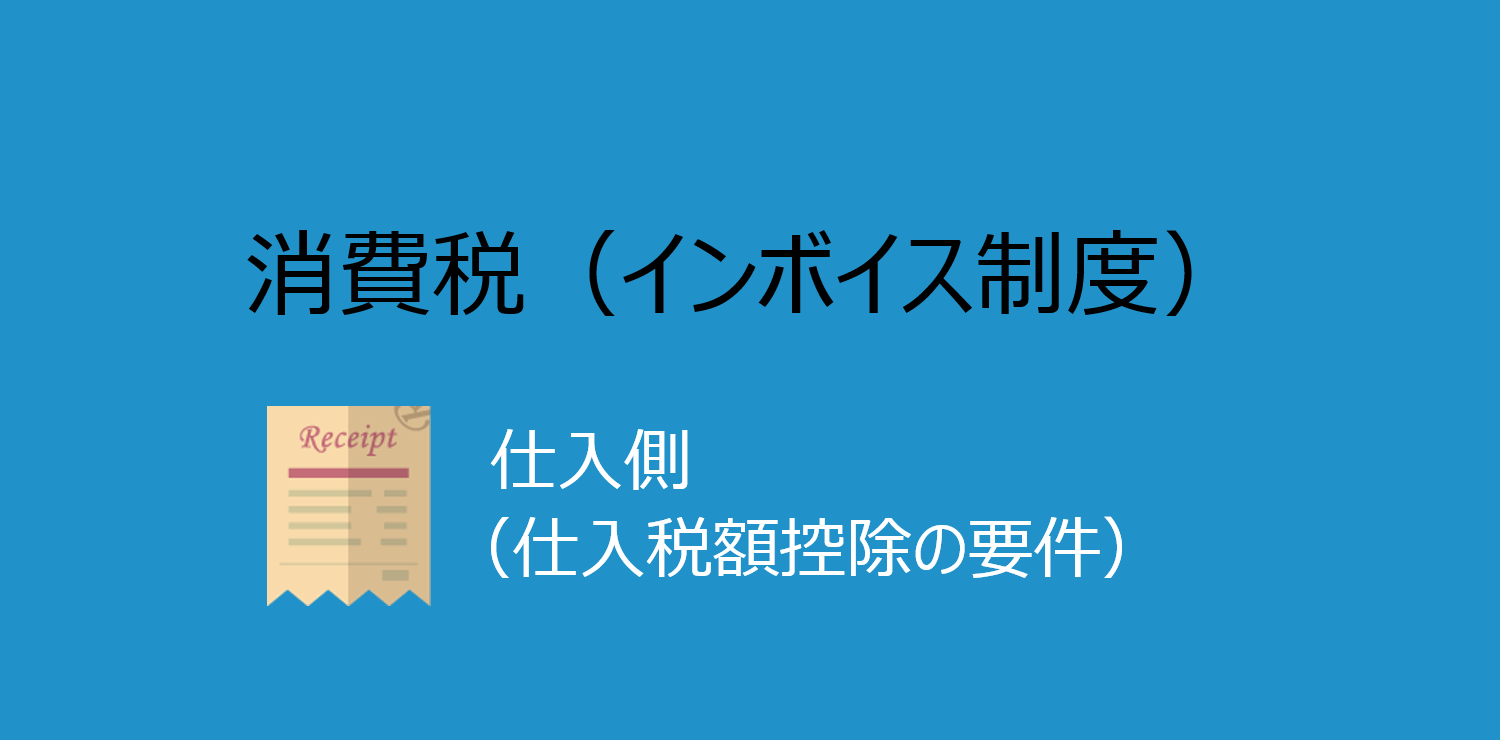
前回に引き続き、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について。
今回も仕入側で考えるべき内容です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 帳簿のみ保存で仕入税額控除が認められる場合
インボイス制度の下では、原則として、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされています。
ただし、「請求書等の交付を受けることが困難である場合」などは、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
「インボイス制度」とか「適格請求書等保存方式」とか大げさに言われると、何となくすべての取引で適格請求書の保存が必要に聞こえますが、帳簿のみの保存で済む場合があるのは、別に今と変わらないということですね。
2. 「3万円未満なら」セーフのもの
ただ、今とは大きく違う点もあります。
現行制度では、少額取引(課税仕入れの支払対価の額の合計額 3 万円未満)については、一定の事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けることができます(つまり、請求書等の保存は不要)。
一方で、インボイス制度の下では、この「3万円未満なら一律セーフ」という取扱いがなくなります。極端な話、100円の課税仕入れでも請求書等が必要な場合があるということです。
ただ、なくなるのは、あくまでも「一律」セーフという取扱いで、「3万円未満ならセーフ」という取扱いは一部残っています。
端的には、売手の側で適格請求書の交付義務が免除されるものですが(売上側の視点はこちら)、施行令や施行規則で挙げられているものをさっぱり書くと、以下のとおりです。
(2) 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
逆にいうと、こういうものでも3万円以上なら、基本的に適格請求書の保存が仕入税額控除の要件になるので、ちゃんと領収書とかをもらわないといけないってことですね。
(1) 交通費(公共交通機関特例)
(1)は、いわゆる「公共交通機関特例」です。
その内容については、通達(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達)でもう少し説明されており、具体的な判定は、「1回の取引の税込価額が3万円未満かどうか」で行います。逆にいうと、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。
Q&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)で挙げられている具体例としては、「東京‐新大阪間の新幹線の大人運賃が 13,000 円であり、4人分の運送役務の提供を行う場合」があり、この場合、「4人分の 52,000円」で判定することとなります。
もう1つ、通達で明確化されているのは、公共交通機関特例の対象範囲で、まとめると以下のとおりです。
(例えば、特急料金・急行料金・寝台料金)
●旅客の運送に直接的に附帯しない対価…公共交通機関特例の対象外
(例えば、入場料金・手回品料金・貨物留置料金)
公共交通機関特例の対象外のほう(つまり、請求書等の保存が必要なほう)を押さえておいたほうがよさそうですね。
要は、こうやって公共交通機関特例の適用範囲を考えて、それが3万円以上なら、適格請求書の保存が必要(仕入税額控除の要件)になるということです。ただし、その場合でも、鉄道事業者から適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を記載した乗車券の交付を受け、その乗車券が回収される場合は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
(2) 自動販売機特例(2021年8月一部追記)
(2)の自動販売機等についても、通達でもう少し説明されており、具体的には、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものを指します。
自動販売機も、こうやって説明すると何かカッコいいですね。「代金の受領と資産の譲渡等が完結する機械装置ですが、何か」みたいな。
Q&Aで例示されているものには、以下があります。
逆に、以下のようなものは、ここでいう自動販売機等による商品の販売等に含まれないものとされています。
上記のうち、コインパーキングについては、別途記事を書きました(こちら)。
その他、当局の人が書いた以下の本では、「有料道路のETC」も自動販売機特例の対象外とされています(ETCの利用証明書による仕入税額控除についてはこちら)。
(3) 3万円以上でも適格請求書の保存が不要なケース
今回の内容とは別の話ですが、3万円以上でも適格請求書の保存が不要なケースについては、以下の記事をご参照ください。
3. 帳簿への追加記載事項(2022年11月一部追記)
最後に、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合の記載事項についてです。
この場合の帳簿の記載事項に関しては、通常の記載事項に加えて、以下の記載が必要になります。
前者については、例えば、(1)3万円未満の公共交通機関による旅客の運送に該当するのであれば、「3万円未満の鉄道料金」のように書いておくということです。
後者については、例えば、(2)3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等に該当するのであれば、「〇〇市 自販機」や「××銀行□□支店ATM」のように書いておくということです(いずれも国税庁のQ&Aで挙げられている例です)。ただ、仕入れの相手方の住所または所在地のほうは、原則は記載が必要とされているものの、記載が不要な場合も多いです。例えば、(1)3万円未満の公共交通機関による旅客の運送であれば、「その運送を行った者の住所または所在地」は記載する必要はありません。
今日はここまでです。
では、では。
↓インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。
6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)
↓インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。
これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
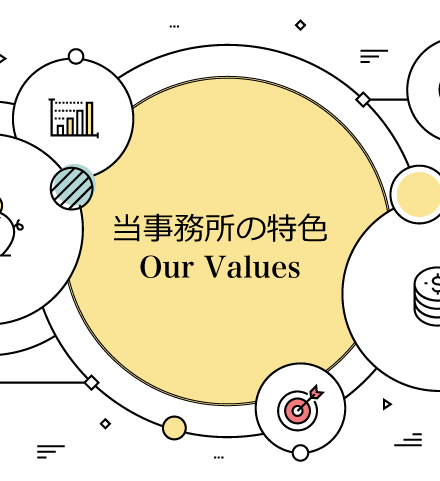
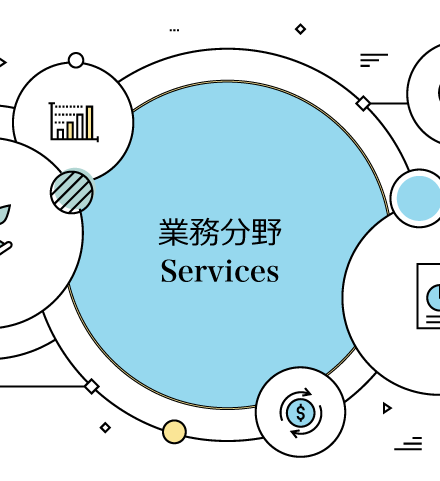
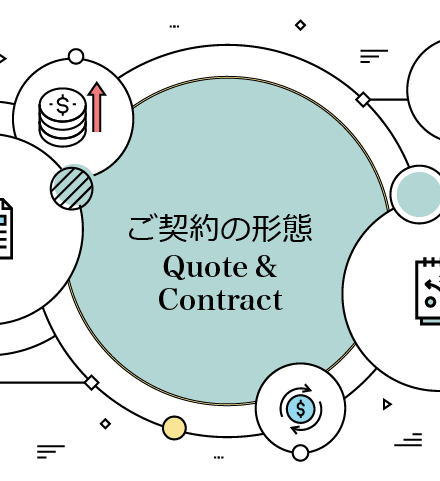
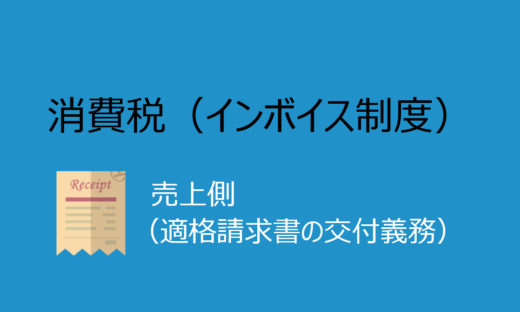
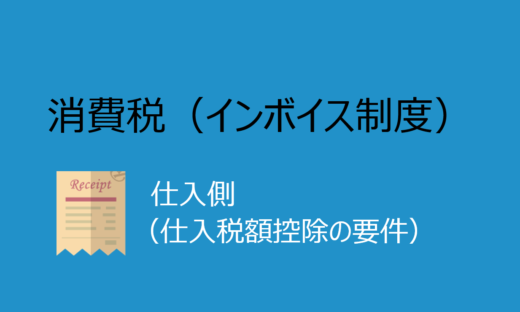
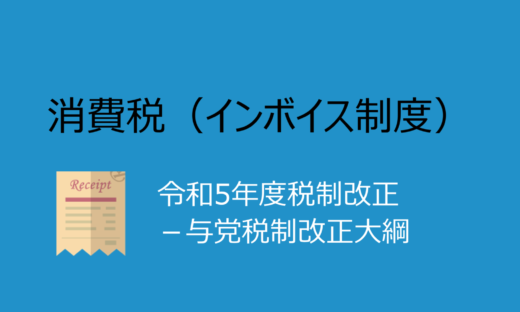
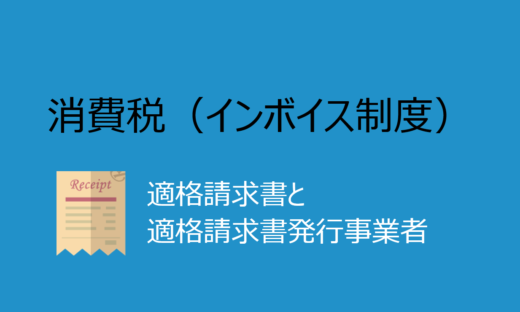
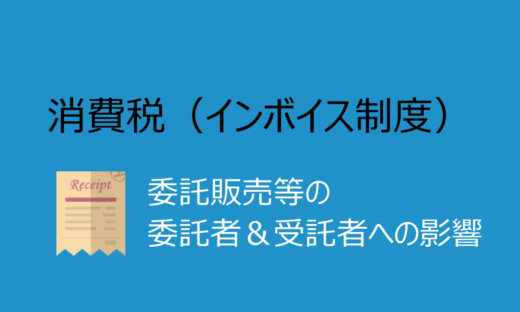
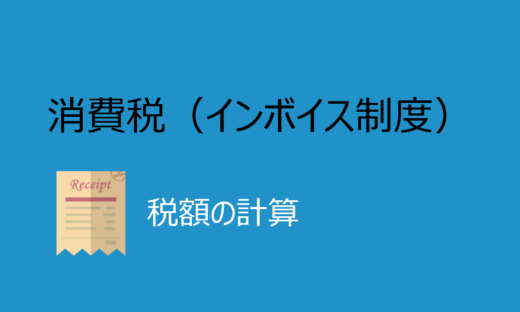


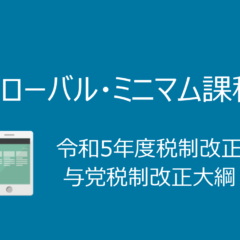
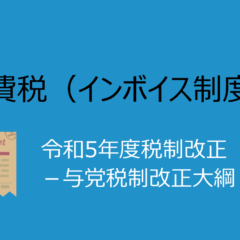
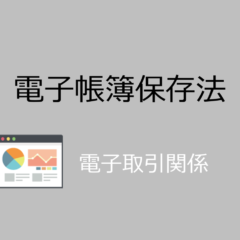
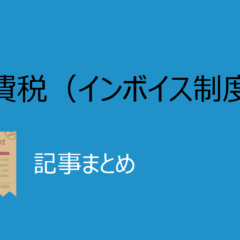

-240x240.png)
-240x240.jpg)
-240x240.png)

-240x240.png)