第6回 移転価格税制における「差異調整」をわかりやすく
.png)
引き続き「独立価格比準法(CUP法)」シリーズです。
ここまで、独立価格比準法が使えるケースと使えないケースを見てきました。
Table of Contents
1. 「そのままでは」独立価格比準法が使えないケース
独立価格比準法が使えるケースは、「そのまま」独立価格比準法が使えるケースだったのですが、実際にはそんなにピッタリ同じ比較対象取引を見つけられるケースは多くないかもしれません。
「比較対象取引としてOKそうだけど、ちょっとだけ違うんだよな」という感じが多いんじゃないでしょうか。例えば、国外関連取引と比べたときに、取引段階や取引規模が違うというような場合です。
2. 差異調整とは
で、こういう場合に考えるべきテーマが「差異調整」です。
「差異調整」とか「差異の調整」とか呼びますが、これは文字どおり、独立企業間価格の算定にあたって、国外関連取引と比較対象取引との差異について調整を行うことを意味します。
ではなく、
「比較対象取引になりそうだ→差異がある→その差異を調整して比較対象取引にしよう」
ということです。
この差異調整の目的は、比較対象取引として選定された非関連者間取引について、比較対象としての合理性を確保することにあります。差異調整という概念について、知っておくべきポイントは2つです。
差異調整は全ての差異を対象とするものではありません。普通に考えて、とてもそんなことはできないので。じゃあ、どういう差異を調整するかと言うと、「国外関連取引の対価の額に影響を及ぼすことが客観的に明らかなもの」を対象にします(そういう判例があります)。具体例は後ほど。
国外関連取引と比較対象取引の差異が、価格(や利益率等)に及ぼす影響を無視できず、かつ、差異による具体的影響額を算定できない場合には、比較可能性自体に問題があるという結論になります。シンプルにいうと、「そもそも比較対象取引にならないレベルの差異があれば、それは調整できないので、あきらめましょう」ということです。
この差異調整は、独立価格比準法だけに関係する話ではありません。他の独立企業間価格の算定方法についても、同様の話があります。ただ、独立価格比準法についてお伝えするのが一番わかりやすいので、そうしているということです。
3. 具体的な差異調整方法
具体的な差異調整の方法として、事務運営指針には以下の4つの例が挙げられています。
貿易条件について、一方の取引がFOB(本船渡し)であり、他方の取引がCIF(運賃、保険料込み渡し)である場合
➡比較対象取引の対価の額に運賃及び保険料相当額を加減算する方法
(2) 決済条件の差異調整
決済条件における手形一覧後の期間について、国外関連取引と比較対象取引に差異がある場合
➡手形一覧から決済までの期間の差に係る金利相当額を比較対象取引の対価の額に加減算する方法
(3) 値引き・割戻し等の差異調整
比較対象取引に係る契約条件に取引数量に応じた値引き、割戻し等がある場合
➡国外関連取引の取引数量を比較対象取引の値引き、割戻し等の条件に当てはめた場合における比較対象取引の対価の額を用いる方法
(4) 機能またはリスクに係る差異調整
機能またはリスクに係る差異があり、その機能またはリスクの程度を国外関連取引及び比較対象取引の当事者が当該機能またはリスクに関し支払った費用の額により測定できる場合
➡その費用の額が当該国外関連取引及び比較対象取引に係る売上または売上原価に占める割合を用いて調整する方法
具体的にどういう調整をするかは、次回、ケースの形で確認します。
なお、差異調整については、独立価格比準法が関係するところではないのですが、2019年度税制改正が影響する部分もあるので、先のほうでもう一度確認したいと思います。
今日はここまでです。
では、では。
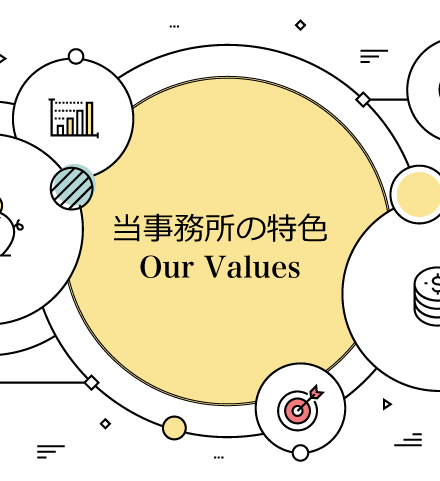
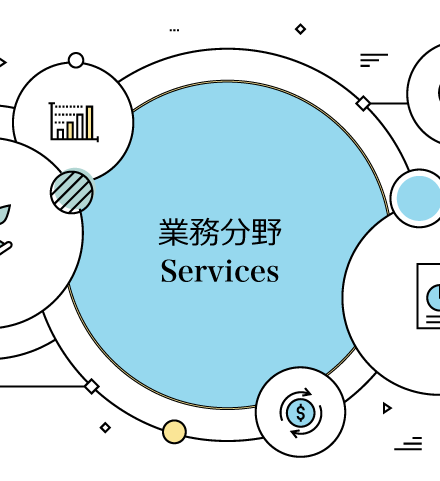
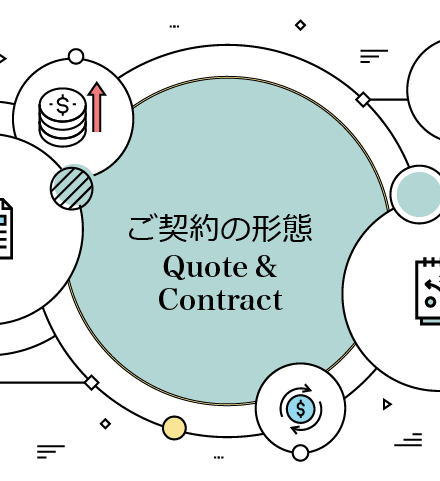
-520x312.png)
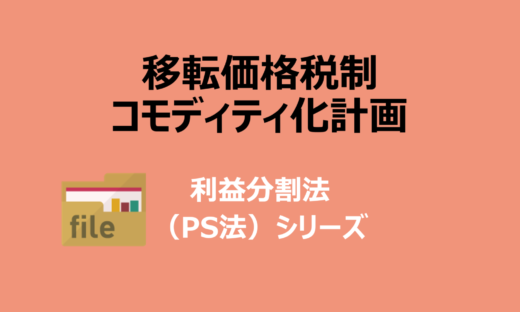
-520x312.png)
-520x312.png)
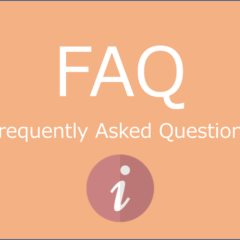


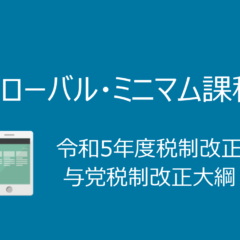
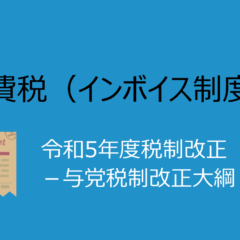
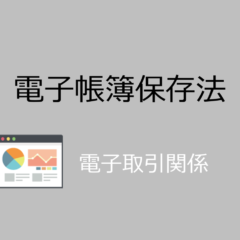
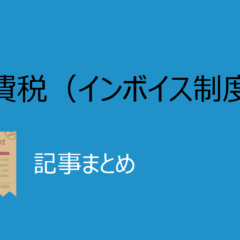

-240x240.png)
-240x240.jpg)
-240x240.png)
