第13回 保証料率算定時のイールド・アプローチとコスト・アプローチ(移転価格税制)
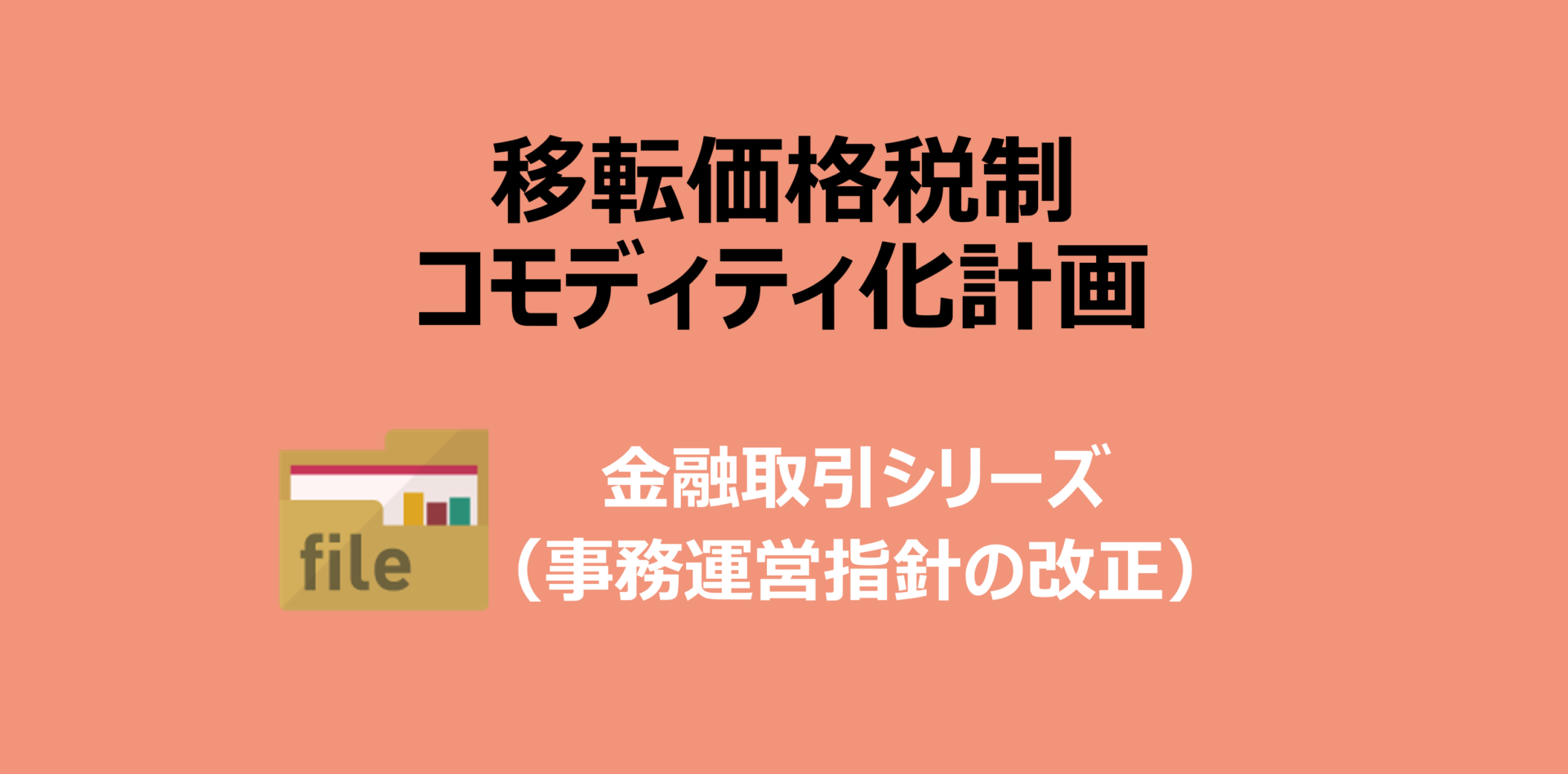
引き続き「金融取引」シリーズです。
今回は債務保証取引に対する保証料率の設定の際のアプローチについて。
このブログの趣旨に反するのですが、ちょっとだけ事務運営指針等々の内容から離れます。
Table of Contents
1. 保証料の算定方法
前提として、債務保証取引の場合、現実に行われる取引の中から比較対象取引を見いだすことは難しいケースも多いので、改正後の移転価格事務運営要領では、いわゆるイールド・アプローチやコスト・アプローチという保証料の算定方法が示されています。
具体的には、債務保証取引に係る独立企業間価格の検討を行う場合、例えば、以下の事項を勘案して想定した取引を比較対象取引とすることができることとされています。
債務保証等の対象である債務の主たる債務者が、「債務保証等が行われていないとした場合」と「債務保証等が行われた場合」のそれぞれにおいて、債権者に対して支払うべき利息等に係る利率等の差
債務保証等の対象である債務の不履行が生ずる場合に、債務保証等を行った者が負担するべき損失の額(債務の不履行が生ずる確率を勘案して算定される損失の額)の債務の額に対する割合
それぞれの内容は、以下でもう少し具体的に確認します。
2. イールド・アプローチとは
イールド・アプローチは、シンプルに言うと、保証料の算定にあたり、債務保証なしの場合とありの場合の金利差をベースにする方法です。
ポイントとしては、視点を被保証者側に置いて、そのベネフィットを考えます。
計算手順を大まかにいうと、以下のとおりです。実際にはもっと色々バリエーションがあります(趣味の世界です)。
(2) 債務保証ありの場合の調達金利(保証者の信用格付等に基づく金利)を算定
(3) 両者の差(イールド・スプレッド)を算定
(4) (3)のイールド・スプレッドを保証者・被保証者に配分する前提で、独立企業間価格(保証料)を算定
事務運営指針ではそこまで読み取れませんが、(3)のイールド・スプレッドは、保証者と被保証者の調達金利の差のイメージであり、言い換えると、債務保証により、調達金利の低減という形で両者が得るメリットです。
ということは、イールド・アプローチにより算定されるのは、基本的に保証料の最大値なので、それを(4)で保証者と被保証者に配分する形になります。
言い換えると、「保証料=イールド・スプレッド」であれば、被保証者側には債務保証を受けるインセンティブがなくなるので、保証者はその一部を被保証者に渡すような形で、保証料率を設定するということです。
ちなみに、(4)のイールド・スプレッドの配分割合については、プロの人に聞いてください。仮に(3)までを精緻に計算したとしても(実際にはできてないですけど)、(4)の配分割合が変われば、保証料率も変わってしまいます。ちなみに、そういう分析を見ていて、私は一度も「なるほどなあ」と思ったことはないです。
3. コスト・アプローチとは
コスト・アプローチは、シンプルにいうと、債務保証の対象である債務のデフォルト確率を勘案して算定した期待損失(率)をベースにする方法です。
イールド・アプローチとは真逆で、ポイントとしては、視点を保証者側に置いて、そのコストを考えます。
計算手順を大まかにいうと、以下のとおりです。実際にはもっと色々バリエーションがあります(完全に趣味の世界です)。
(2) リスク負担に伴う対価((1)への上乗せ額)を算定
(1)は、基本的に外から買ってくるデータであり、保証者側の期待損失(率)です。
コスト・アプローチにより算定されるのが(1)だけだとすれば、それは基本的に保証料の最小値になります。なので、 (2)でリスク負担に伴う対価を上乗せする形になるんじゃないでしょうか(そうすると、純粋なコスト・アプローチではなくなるので、国税庁がこの点をどう考えているかはよくわかりませんが)。
言い換えると、「保証料=期待損失」であれば、保証者側には債務保証を行うインセンティブがなくなるので、保証者は追加の対価を上乗せするような形で、保証料率を設定するということです。
ちなみに、(2)のリスク負担に伴う対価の算定方法については、プロの人に聞いてください。実際には、その計算により保証料率も変わってしまうわけですが、私は一度も「なるほどなあ」と思ったことはないです。
4. 両アプローチの関係
両者の関係ですが、イールド・アプローチにより算定されるのは、基本的に保証料の最大値です。債務保証してもらう側には、それ以上支払う理由がないので。
一方、コスト・アプローチにより算定されるのは、基本的に保証料の最小値です。債務保証する側は、それ以上もらわないと割に合わないので。
なので、独立企業間価格(保証料率)は、たぶん両アプローチの算定結果の間にあります。そもそも、どっちもちゃんと計算できてる気がしないので、単なる概念上の遊びに過ぎませんが。
ただ、パブリック・コメントに対応する形で示された「国税庁の考え方」では、イールド・アプローチとコスト・アプローチ(またはその他の方法)のどれか1つの方法だけを適用している場合であっても、それが最も適切な方法と認められる場合もあるとされています。参考事例集では、両アプローチの算定結果の平均値を使ったりもしていますが、日本の当局の考え方では、必ずしも両者の間ということでもないのかもしれません。
ちなみに、保証者と被保証者の信用格付等が同一の場合(そういうケースもあります)、イールド・アプローチは使えませんが、コスト・アプローチは使えます。
今日はここまでです。
では、では。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
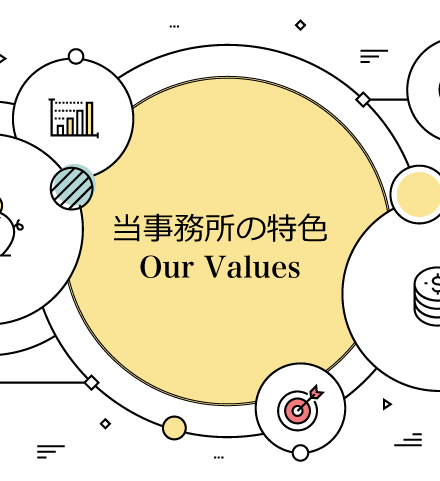
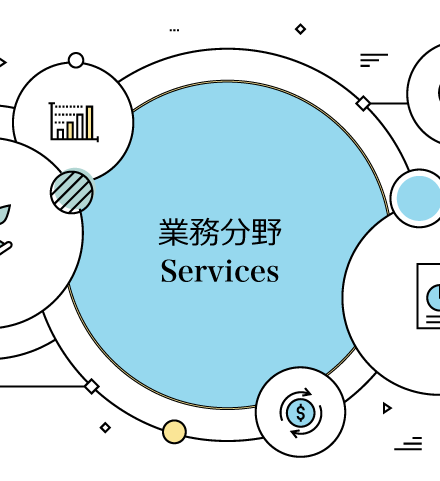
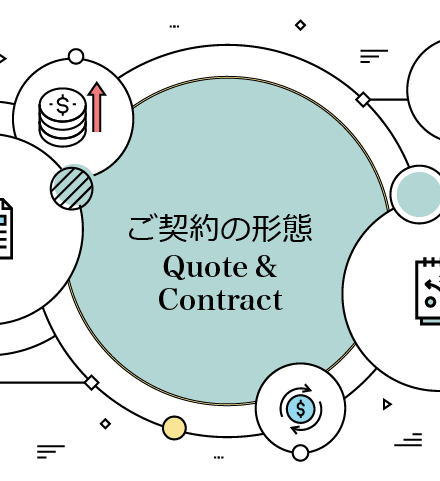
-1-520x312.png)
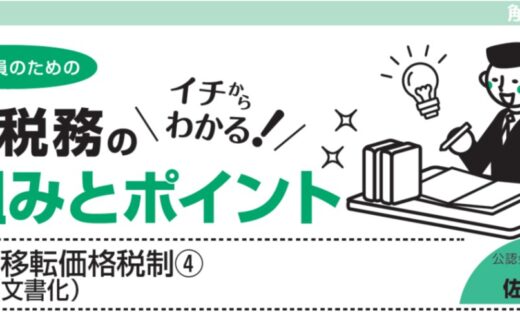
-520x312.png)
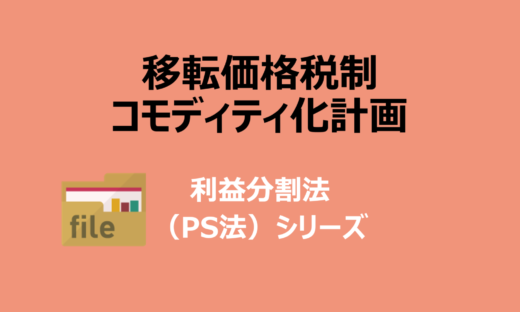
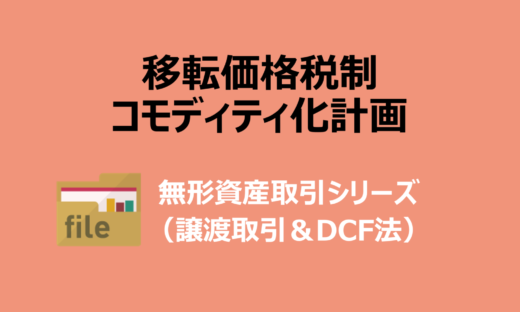
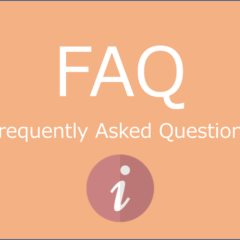


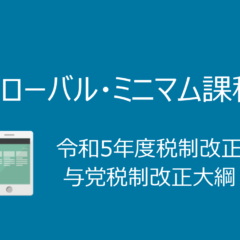
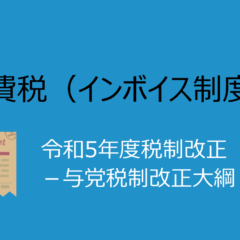
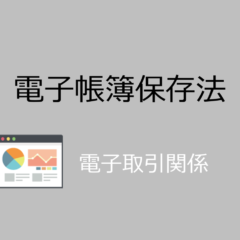
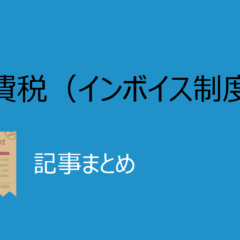

-240x240.png)
-240x240.jpg)
-240x240.png)
