一時差異等加減算前課税所得とは(繰延税金資産の回収可能性)
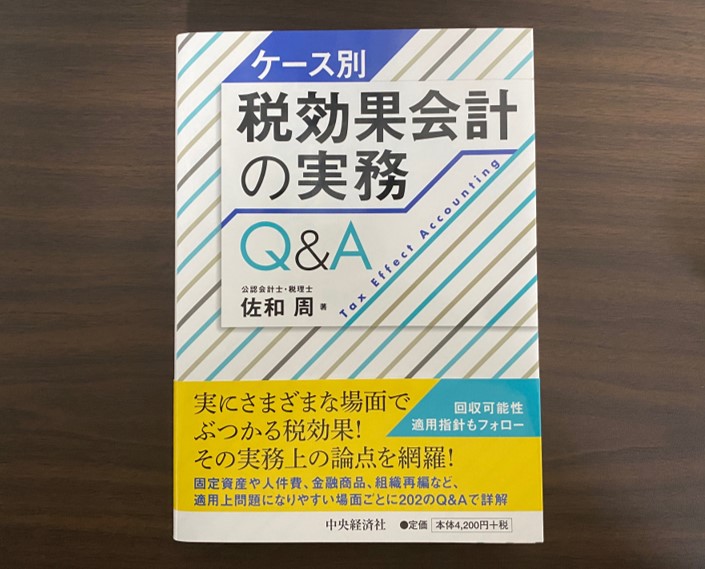
2016年に書いた『ケース別 税効果会計の実務Q&A』という本ですが、コンテンツを自由に使えるようになったので(経緯はこちら)、いつか紙の本じゃない形で書き直そうと思っており、それまでの間、その内容を少しブログに書きたいと思います。
今日は、今週のセミナーで取り扱う内容に関連するテーマです。
Table of Contents
1. 今回のテーマは一時差異等加減算前課税所得
上記の本では時期の問題で、またセミナーでは難易度の問題で、それぞれあまり詳細には触れていない内容なのですが、今回のテーマは一時差異等加減算前課税所得です。
繰延税金資産の可能性の検討にあたっては、一時差異等加減算前課税所得の見積りが必要になります。端的には、これと、将来の将来減算一時差異の解消予定なんかを当てて、税金の減額効果を考えるという位置付けです。
2. 一時差異等加減算前課税所得とは
まず、定義からですが、「一時差異等加減算前課税所得」とは、将来の事業年度における課税所得の見積額から、当該事業年度において解消することが見込まれる「当期末に存在する」将来加算(減算)一時差異の額を除いた額をいいます(控除が見込まれる繰越欠損金の額も除きます)。
ポイントは、「当期末に存在する」一時差異の額(の解消)に限って、除外するという点です。
3. 「課税所得」か「一時差異等加減算前課税所得」か
文脈として、「一時差異等加減算前課税所得」というのは、基本的に将来の見積りについて使う用語で、過去の実績については単純に「課税所得」という用語を使います。
つまり、過去における将来減算一時差異解消時の税金負担額を軽減効果の実績を把握する際には「課税所得」を見ます。
一方で、当期末に存在する将来減算一時差異について、将来における解消時に税金負担額の軽減効果を有するかどうかを判断する際には「一時差異等加減算前課税所得」を見るということです。一時差異等加減算前課税所得は、将来減算一時差異に当てるものなので、当然ながら「一時差異等加減算前」じゃないと筋が通らないということです。
4. 数値例(適用指針の設例)
はあ?という感じかもしれないので、簡単な数値例で見てみます。
適用指針の設例の前提条件を使って、翌期と翌々期の一時差異等加減算前課税所得の見積額を軽く算定してみます。
(1) 翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積り
翌期の課税所得の見積額の算定過程が以下であると仮定します(細かな設定は適用指針の設例をご覧ください)。
この場合、翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額は850です。
課税所得の見積額が440で、当期末に存在する将来減算一時差異の解消見込みが△410(=賞与引当金認容△400+減価償却超過額認容△10)なので、減算前なら850ということで。
混乱するとしたら、翌期における新たな将来減算一時差異の発生くらいでしょうか。上記でいうと、「賞与引当金繰入限度超過額 350」ですね。これは、一時差異等加減算前課税所得の計算にあたってカウントされます。当期末に存在するものじゃないので、加算前に戻す必要はないということです。
(2) 翌々期の一時差異等加減算前課税所得の見積り
その続きで、翌々期の課税所得の見積額の算定過程が以下であると仮定します(細かな設定は適用指針の設例をご覧ください)。
この場合、翌々期の一時差異等加減算前課税所得の見積額は500です。
課税所得の見積額が490で、当期末に存在する将来減算一時差異の解消見込みが△10(=減価償却超過額認容△10)なので、減算前なら500ということで。
「翌々期における新たな将来減算一時差異の発生」や「翌々期における翌期発生予定の将来減算一時差異の解消」は一時差異等加減算前課税所得の計算にあたってカウントされます。当期末に存在するものじゃないので、加減算前に戻す必要はありません。
5. 最後に
色々と捨象してますけど、シンプルにいうとこんな感じです。
賞与引当金のように、「超過→認容」というサイクルのものが多ければ、翌期だけ一時差異等加減算前課税所得が大きくて、翌々期以降は同じような感じというイメージになるんじゃないでしょうか。
今日はここまでです。
では、では。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
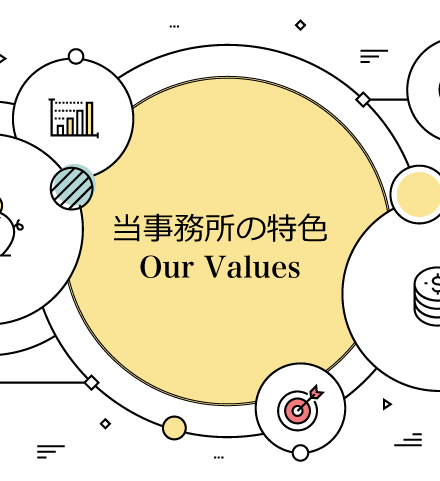
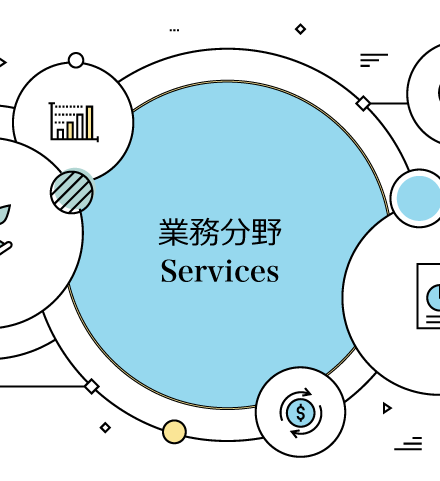
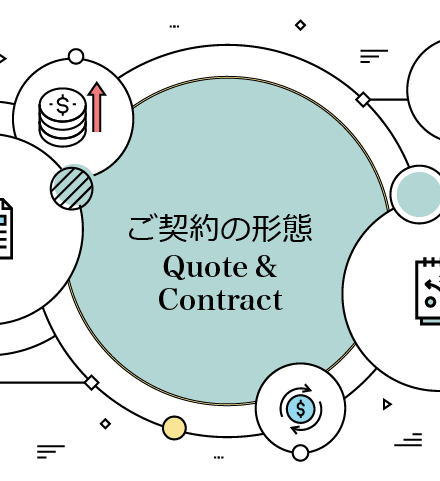
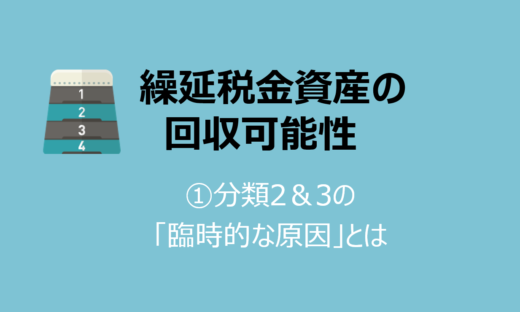
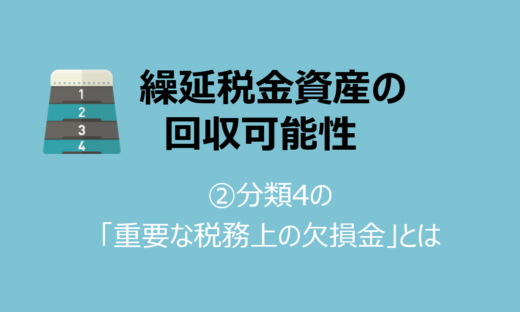
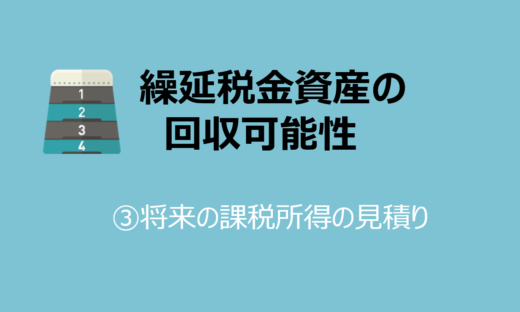
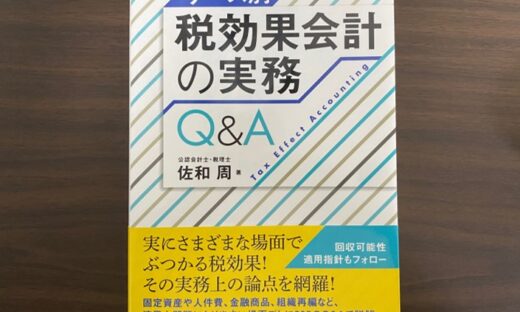




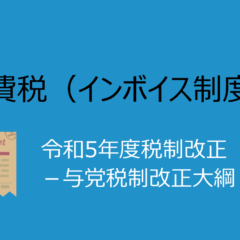

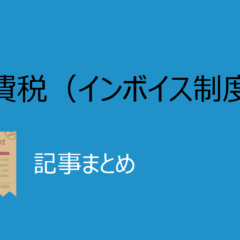

-240x240.png)
-240x240.jpg)
-240x240.png)
