第11回 利益分割法(PS法)における「分割要因」とは
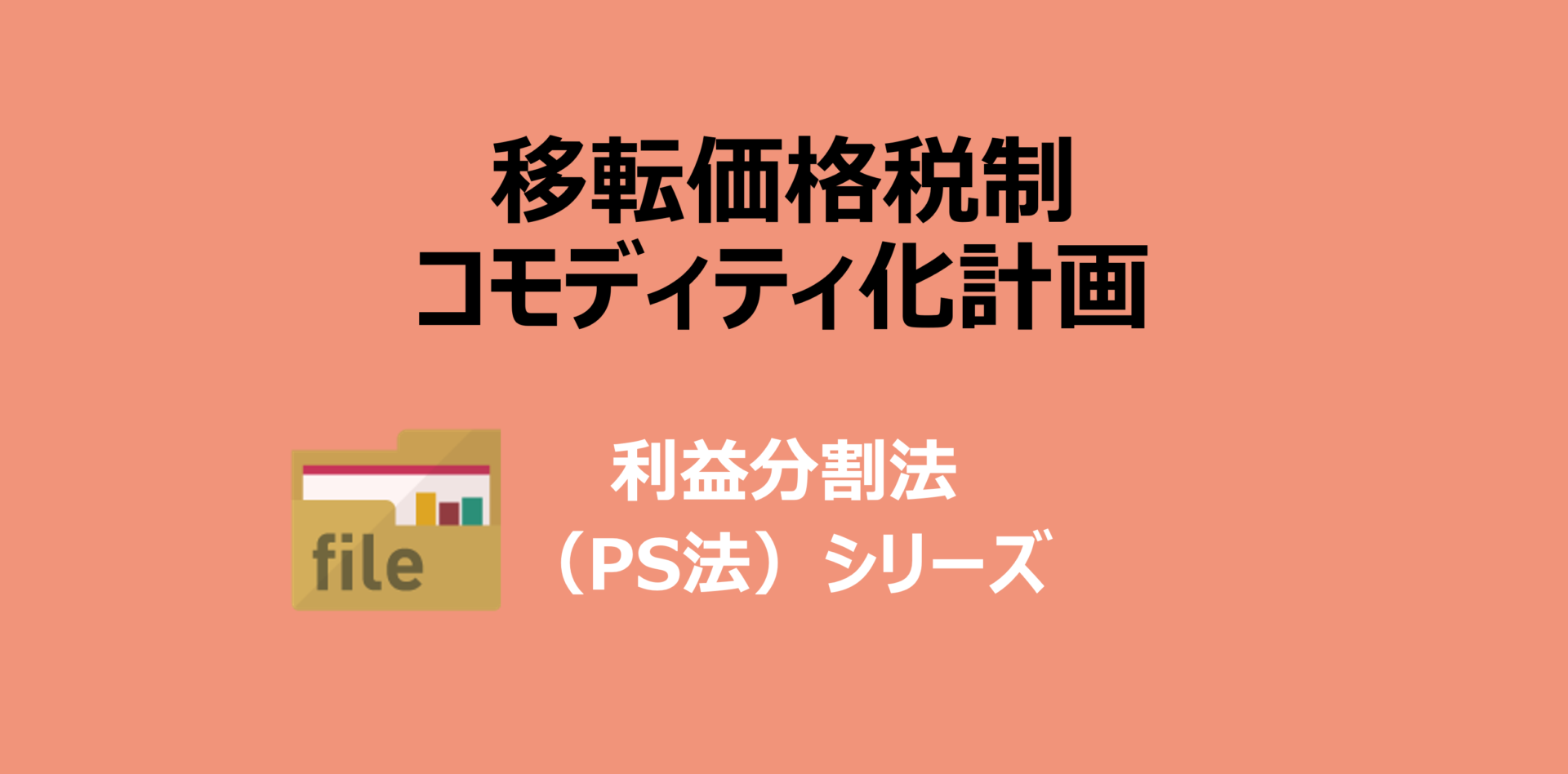
引き続き「利益分割法(PS法)」シリーズです。
Table of Contents
1. 分割要因とは
寄与度利益分割法や残余利益分割法においては、分割対象利益等を何らかの基準で自社と国外関連者に配分する必要があります。
この配分にあたって必要になるのが「分割要因」です。「分割ファクター」と呼ばれることもあります。
なので、利益分割法における計算要素は、主に「分割対象利益等」と「分割要因」といえます。
2. 寄与度利益分割法の分割要因
まず、寄与度利益分割法について確認します。
寄与度利益分割法は、国外関連取引に係る分割対象利益等を、寄与度に応じて、これらの者に配分することにより、独立企業間価格を算定する方法です。
つまり、この場合の分割要因は、「分割対象利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるもの」でなければなりません。
実際には、何らかの費用の額や使用した固定資産の価額が分割要因として使われます。
3. 寄与度利益分割法の分割要因のイメージ
具体的には、例えば、自社も国外関連者も販売会社であるケースを考えてみます。
前提条件は、以下のとおりとします。
この場合、分割対象利益等は、営業利益の合計である100です。
分割要因は、営業部員の人件費の金額であり、「自社160:国外関連者40」、つまり、「自社4:国外関連者1」です。
したがって、分割対象利益等の100を「自社4:国外関連者1」という分割割合で配分すればよいことになります。
その結果、自社には80(=100×4/5)、国外関連者には20(=100×1/5)の営業利益が配分されることになります。
これはポイント集(国税庁 「移転価格税制の適用におけるポイント」)に挙げられている例をベースにしたものですが、寄与度利益分割法の場合、こんな感じで計算は簡単です。
4. 残余利益分割法の分割要因はもうちょっと先で
次に、残余利益分割法について。
残余利益分割法は、自社及び国外関連者の双方が無形資産を使用して独自の機能を果たしており、双方による独自の価値ある寄与が認められる場合に適用される算定方法です。
残余利益分割法においては、 分割対象利益等から基本的利益を除いた残余利益等を配分しますが、この場合の分割要因については、先のほうで詳細に確認します。
5. 分割要因が複数ある場合
これは寄与度利益分割法でも残余利益分割法でも同じですが、通達では、配分に用いる分割要因が複数ある場合には、それぞれの要因が分割対象利益等または残余利益等の発生に寄与した程度に応じて、合理的に計算することとされています。
要は、各要因のウェイト付けを行うってことですね。
今日はここまでです。
では、では。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
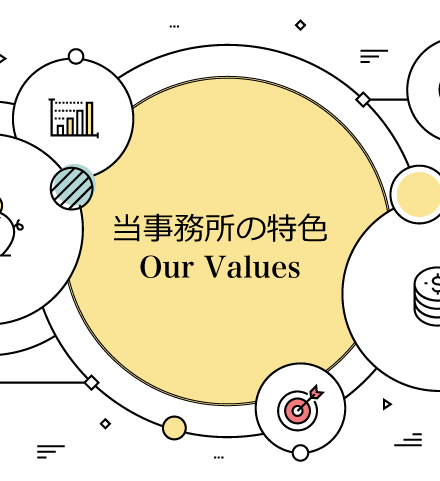
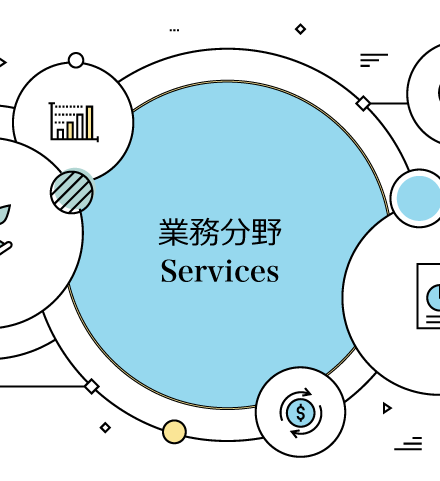
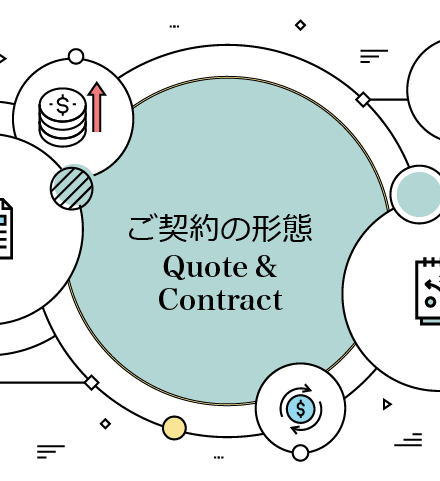
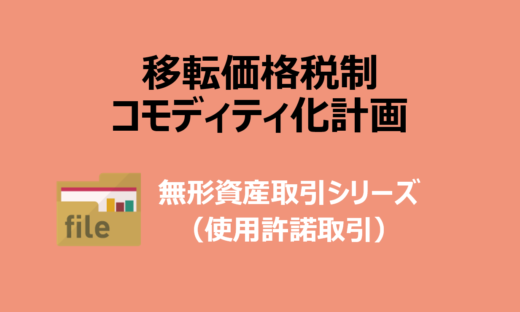
-520x312.png)
-1-520x312.png)
-520x312.png)
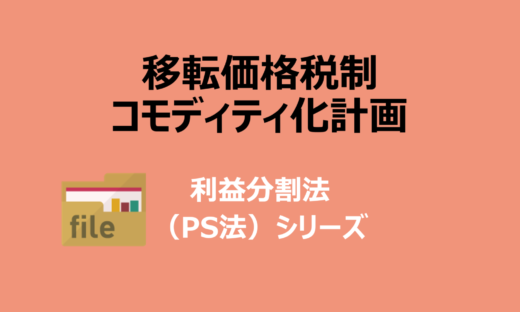
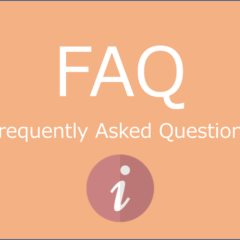


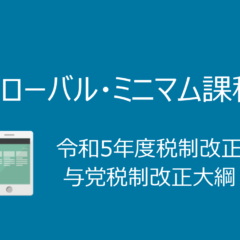
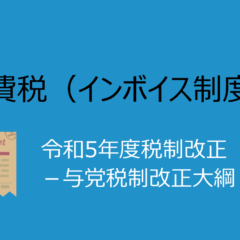
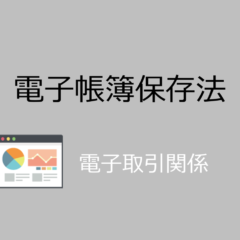
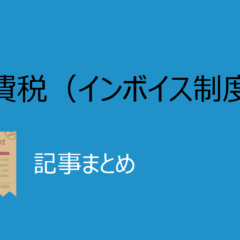

-240x240.png)
-240x240.jpg)
-240x240.png)
