第9回 移転価格税制における「営業利益」とは
.png)
引き続き「取引単位営業利益法(TNMM)」シリーズです。
Table of Contents
1. TNMMにおける営業利益の位置付け
いまは取引単位「営業利益」法を見ているので、チェックすべき利益水準は基本的に営業利益ベースです(営業費用売上総利益率もありますが)。
でも、営業利益って何でしょうか?
2. 営業利益とは
一般に、営業利益とは、通常の営業活動から生じた利益を指します。本業の収益力を示すので、最終損益以外では、最も重要な段階損益だと思います。
EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation:利息・税金・減価償却費等控除前利益)なども重視される指標ですが、これも「営業損益+減価償却費」に近似します。
移転価格税制とはあまり関係ないですが、このあたりは『この取引でB/S・P/Lはどう動く? 財務数値への影響がわかるケース100』という書籍に色々と書きました。
3. 移転価格税制における営業利益とは
話を戻すと、取引単位「営業利益」法は、その名のとおり、基本的に営業利益を使います(売上総利益を使う場合もありますが)。
このとき、国外関連取引に係る検証対象(の当事者)の営業利益については、原則として、本業である企業の営業活動に伴い計上された損益のうち、国外関連取引に直接または間接に関係があるものを用いることとされています。
言い換えると、仮に営業外損益や特別損益に属するような項目が営業利益に含まれていれば、これらは一般的には除外する必要があります。
この話は、検証対象(例えば、海外子会社)というよりは、どちらかというと、比較対象取引の選定に係る作業のほうに当てはまる話です。つまり、比較対象(企業や事業)の営業利益を確認するときにも、国外関連取引に係る利益指標と一貫性のある指標を決定する必要があるということです。
ちょうど財務デュー・デリジェンス(DD)で、正常収益力を分析する、というか調整後EBITDAを算出する過程をイメージして頂けるとわかりやすいのではないかと思います。そっちのほうがわかりにくいという方もいらっしゃるでしょうけど。
4. 海外子会社の損益管理も営業利益率で
ちなみに、海外子会社の損益管理をするときも、営業利益で見ておくことは非常に重要です。
海外子会社の損益管理について、年初に営業利益率の目標レンジを伝えて、その枠内で運用してもらい、イレギュラーなことが起こったら、随時対応するような形はよく見かけます。
今回は、このブログの移転価格税制のテーマからは外れてしまいましたが、ちょっと余談ということで。
では、では。
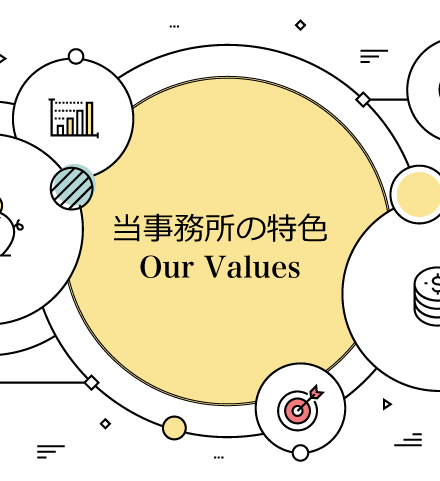
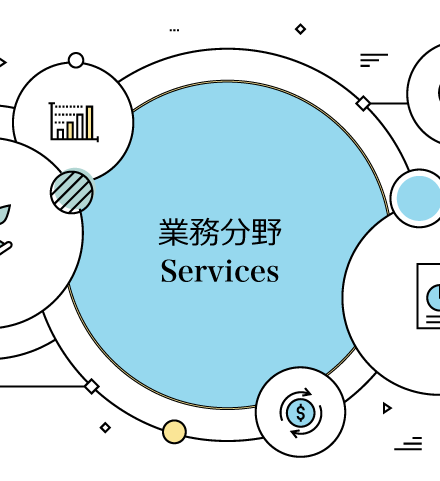
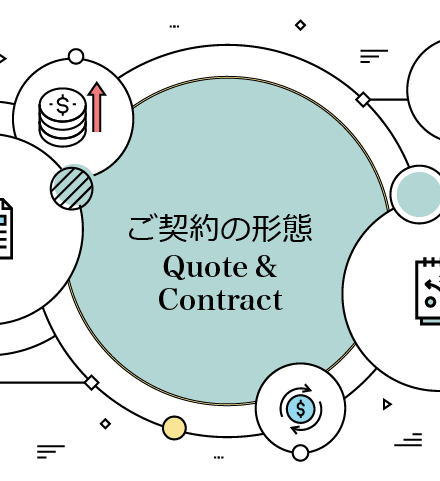
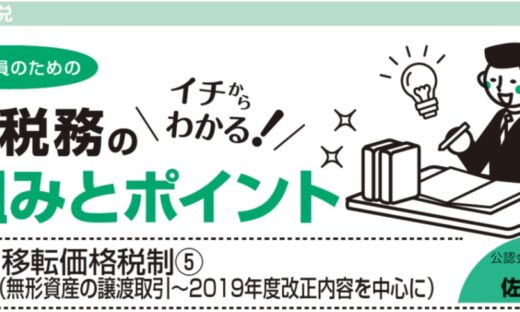
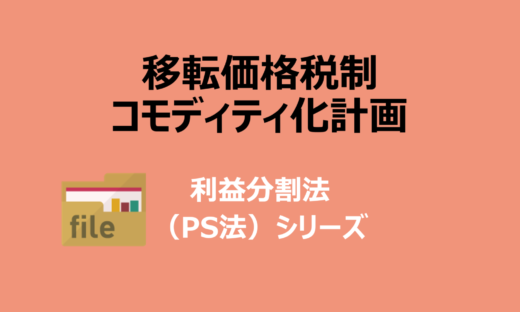
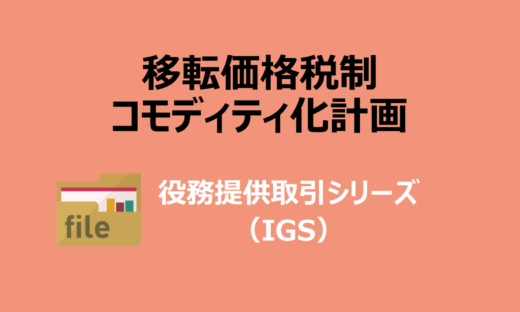
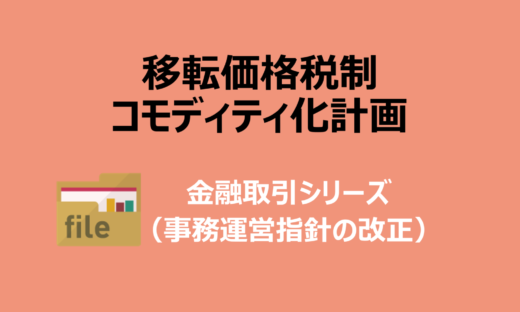
-520x312.png)
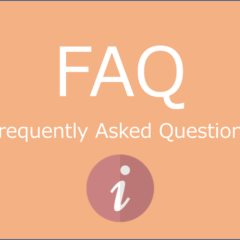


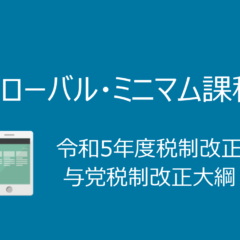
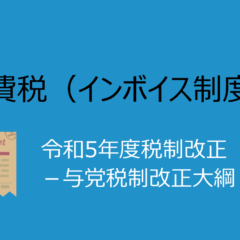
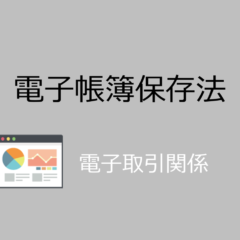
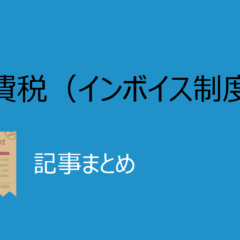

-240x240.png)
-240x240.jpg)
-240x240.png)
