グローバル・ミニマム課税:選択適用の調整項目⑥ 一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例
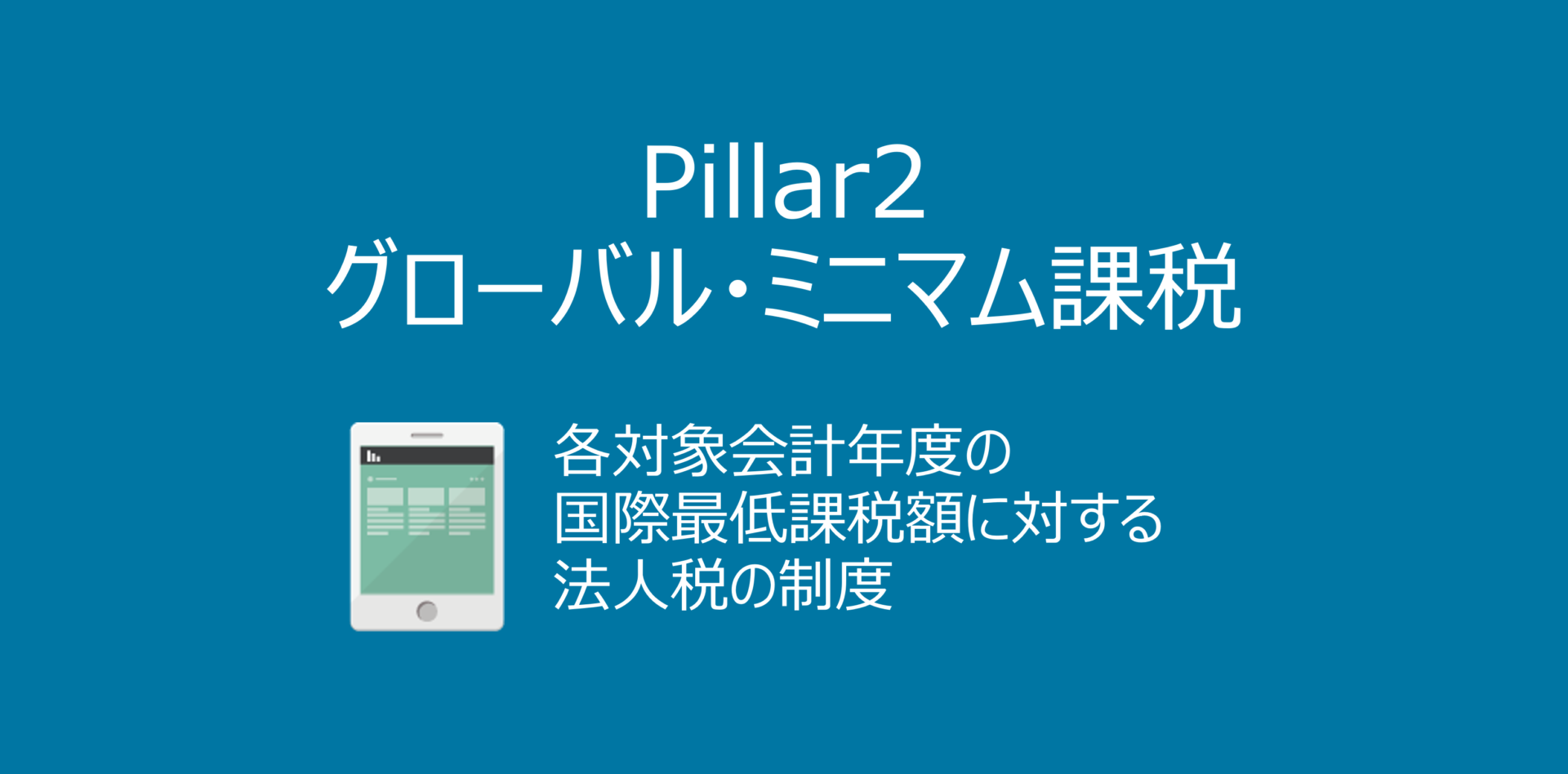
いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています(全体の構成はこちら)。
今回は、選択適用が認められる調整項目の6つ目で、一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例について。
Table of Contents
1. 調整内容要約
まず、さっぱりと調整内容を書くと、以下のとおりです。
調整の概要:上記損益を個別計算所得等の金額から除外する調整
選択:個社・5年
2. 一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例
この特例は、会計上(連結財務諸表上)、海外子会社などの持分に係る為替リスクについて、いわゆる純投資ヘッジを行っている場合の話です。
もう少し言うと、連結財務諸表上はヘッジ手段に係る損益がOCIとして計上される一方、個別財務諸表上はヘッジ手段に係る損益がそのまま当期純損益金額に含められているケースです。
そして、選択適用が認められる調整の内容としては、「個別計算所得等の金額の計算にあたり、当期純損益金額に含まれる純投資のためのヘッジ手段に係る損益を除外する」というものです。
ちなみに、ここでのヘッジ手段は「特定取引」と呼ばれ、これはポートフォリオ持分以外の所有持分(除外資本損益のところで出てくるやつ)の価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるための取引(有効なもの)を意味します。
具体的な調整内容としては、その特定取引に係る為替相場の変動による損失または利益の額について、「特定連結等財務諸表上はOCIで処理される一方、当期純損益金額に係る(つまり、個別財務諸表上の)損失または利益の額と処理されている金額(非対称外国為替差損益以外)」があれば、(特例適用前)個別計算所得等の金額に加算または減算します。
また、上記のとおり、この特例は、個社ごとの5年選択とされています。
3. 特例の趣旨
特例の趣旨は、(国別)実効税率の歪みを解消することにあるとされていますが、どちらかというと、ヘッジ対象に係る損益とヘッジ手段に係る損益をマッチさせる感じだと思います。
というのも、ヘッジ対象はポートフォリオ持分以外の所有持分なので、ヘッジ対象に係る損益(時価評価損益など)は除外資本損益として個別計算所得等の計算から除外されます(たぶん)。なので、ヘッジ手段に係る損益のほうも除外しておくという流れです。
今回はここまでです。
では、では。
グローバル・ミニマム課税に関するオススメの書籍はこちら
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
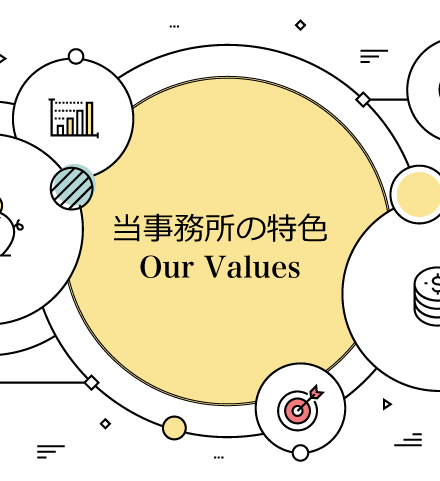
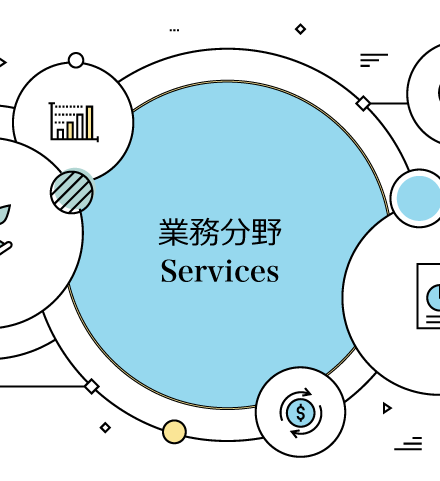
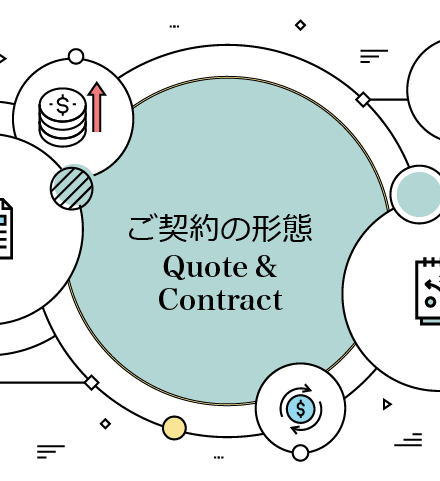
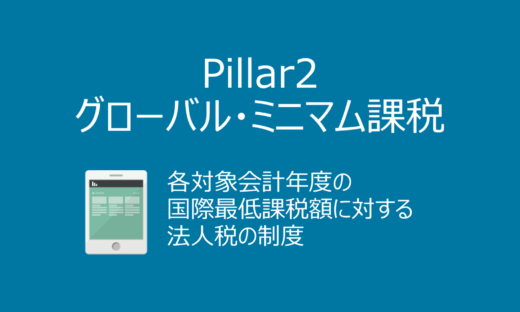
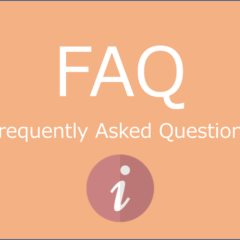


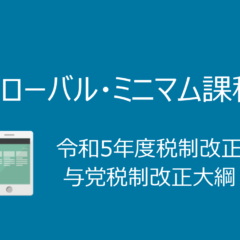
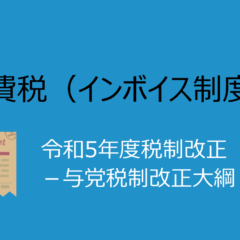
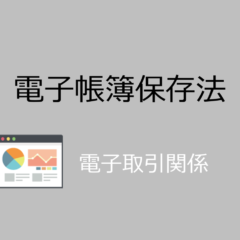
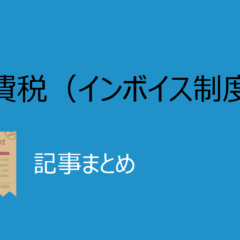

-240x240.png)
-240x240.jpg)
-240x240.png)
