グローバル・ミニマム課税:選択適用の調整項目② 株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例
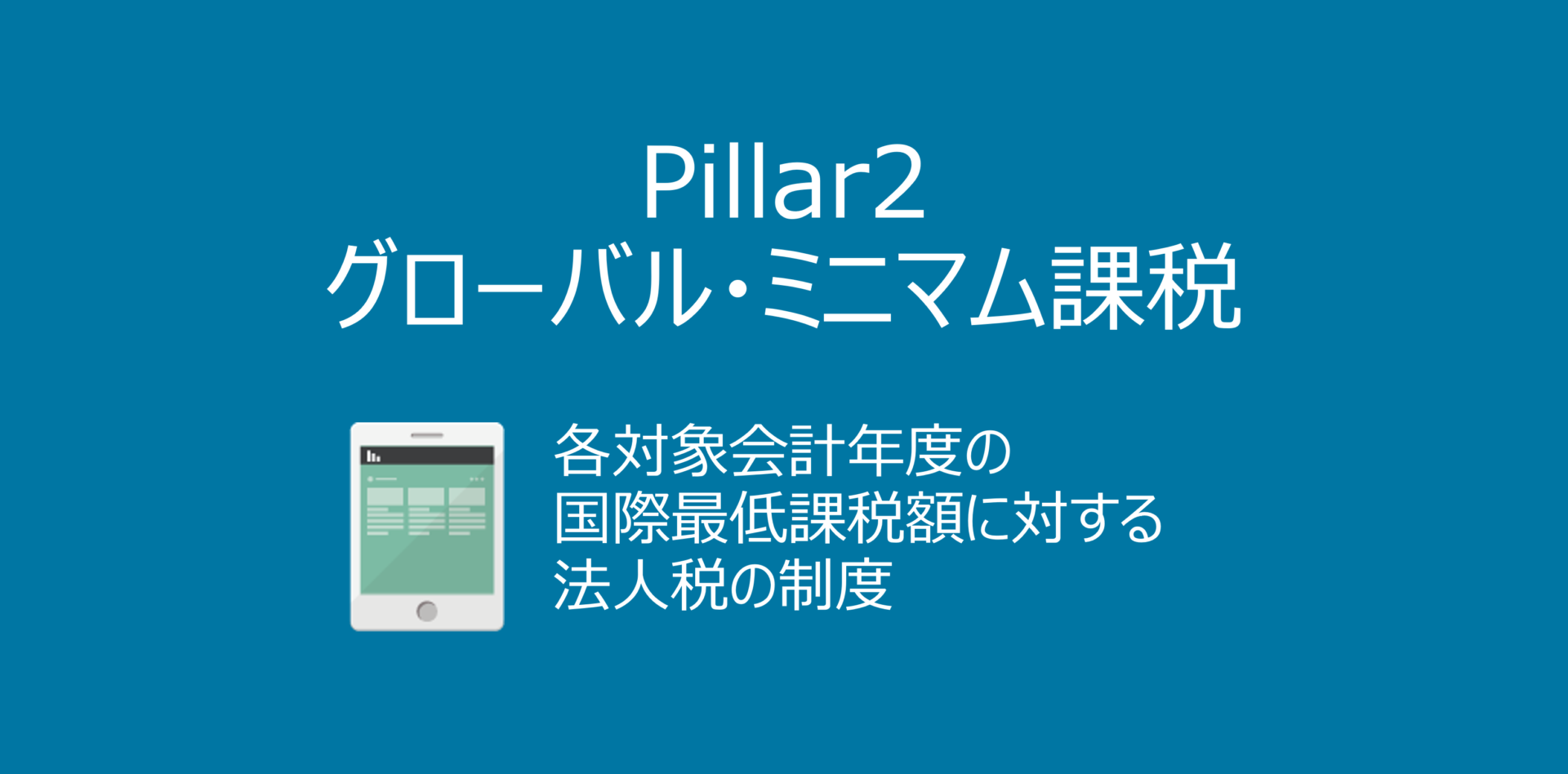
いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています(全体の構成はこちら)。
今回は、選択適用が認められる調整項目の2つ目で、株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例について。
Table of Contents
1. 調整内容要約
まず、さっぱりと調整内容を書くと、以下のとおりです。
調整の概要:税務上の株式報酬費用の取扱いと一致させる調整
選択:国別・5年
2. 株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例
この特例は、構成会社等に株式報酬費用(ストック・オプション等)が発生している場合の話です。
そして、選択適用が認められる調整の内容としては、「個別計算所得等の金額の計算にあたり、会計上の株式報酬費用の額に代えて、税務上の損金算入額を用いる」というものです。
また、上記のとおり、この特例は、国別の5年選択とされています。
3. 特例の趣旨
グローバル・ミニマム課税から離れて考えると、株式報酬費用については、会計と税務で取扱いが異なるケースがあります。
ストック・オプションのような持分決済型の株式報酬の場合、会計上は、その発行時の公正価値を権利行使期間にわたって徐々に(各期に発生したと認められる額を)費用計上していく一方、税務上は、それとは異なる金額(例えば、権利行使時の時価)を損金算入額とするようなパターンです。
これをそのままにしておくと、(国別)実効税率の分母子がズレることになります(たぶん)。
なので、これを解消するために、株式報酬費用については、個別計算所得等の金額の計算にあたり、税務上の損金算入額を使って計算する選択が可能になっているということです。
イメージとしては、分母を分子に合わせる感じだと思います。
4. 具体的な調整内容
この特例を選択した場合、その適用中の年度については、以下の調整を行うことになります。
・税務上の(=法人税等に係る)株式報酬費用額を特例適用前個別計算所得等の金額から減算
また、この特例を受けた後、(法人税等に係る株式報酬費用額に関する)株式や新株予約権等の権利が失効した場合には、上記により減算した金額を失効年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する必要があります。
なお、選択初年度については、一定の調整が必要になるケースがありますが、正確に書くのがめんどくさい(というか、書いたら間違えそうな)ので割愛します。
5. 通達に書いてあること
ちなみに、あんまりメジャーな内容ではないのですが、この特例に関する通達(法基通18-1-56)の内容も書いておきます。
個人的に遭遇したケースというだけです。
内容としては、単純にいうと、構成会社等の役員や従業員から受ける役務の提供等につき、(自社ではなく)その親会社の株式等を交付する場合、(親会社ではなく)その構成会社等においてこの特例の適用があるというものです。
状況としては、構成会社等が非上場、その親会社が上場会社の場合に、子会社である構成会社等の役員や従業員に、上場親会社の株式を交付するようなパターンです(個人所得税の取扱いがめんどくさいやつ)。
この場合、株式を発行している親会社と株式の交付の対象となる役務提供等を受けた子会社(構成会社等)のどちらで特例の適用を受けるのか、という話になりますが、これは前者ではなくて後者だということです。当然ですけど。
今回はここまでです。
では、では。
グローバル・ミニマム課税に関するオススメの書籍はこちら
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
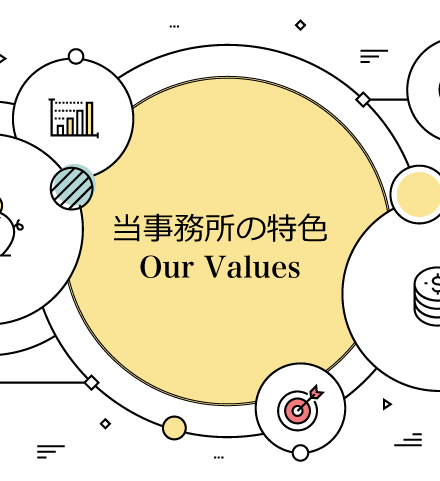
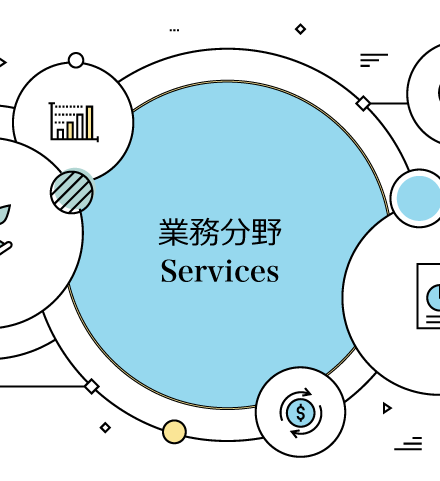
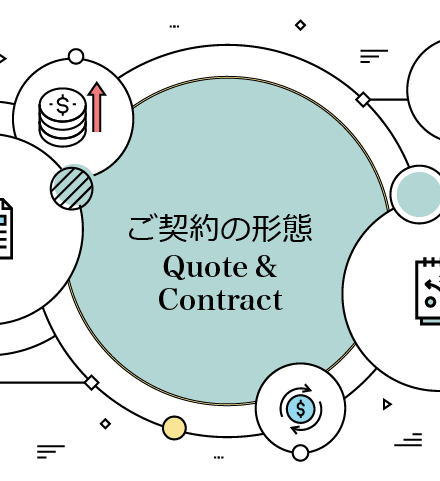
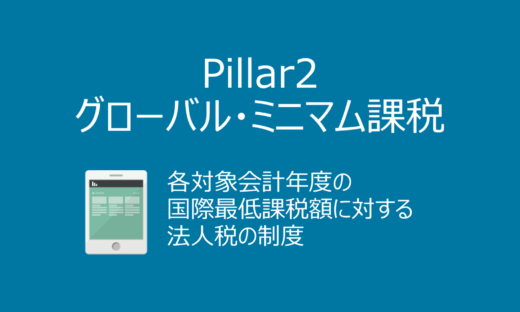
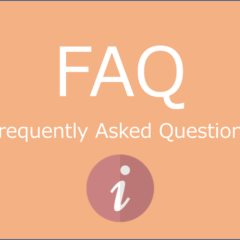


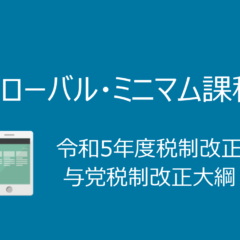
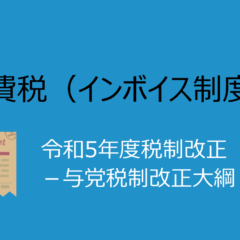
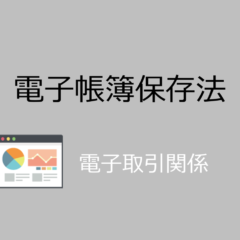
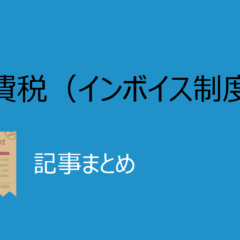

-240x240.png)
-240x240.jpg)
-240x240.png)
